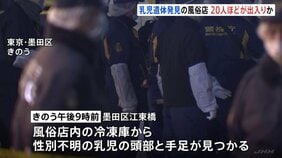南海トラフ地震への備えです。
南海トラフ沿いで、比較的規模の大きな地震が起きた場合や異常な現象が観測された場合、気象庁が「臨時情報」というものを発表することになっています。
この「臨時情報」は、南海トラフ巨大地震につながる可能性があるのかどうか調査を始めたことなどを伝え、巨大地震の可能性が「高まっている」とされた場合、津波からの避難が間にあわない住民などに自治体が自主的な避難を呼びかける可能性があります。

30日は、宮崎県と連携協定を結んでいる京都大学防災研究所が、自治体職員を対象にしたセミナーを開き、「臨時情報」が発表された際の対応について考えました。
県庁で開かれたセミナーには、県内沿岸部の自治体職員が参加しました。
セミナーでは、京都大学防災研究所の矢守克也教授と山下裕亮助教が、南海トラフ地震に関する「臨時情報」が発表された際は、「災害発生に備える大切さを住民に伝えることが重要」などと説明しました。
このあと、今年6月に「臨時情報」に関する訓練を実施した新富町の担当者が訓練で浮かび上がった課題について報告しました。
(新富町総務課危機管理係 黒田修さん)
「もっとふだんから災害が起きたらどうするのかという見地に立って業務をやるべきだという意見をもらった」
(参加者)
「今後の訓練のあり方にいかしていきたいと思っている」
「(市の防災計画の)見直しをこの会の内容を踏まえて行っていきたい」
(京都大学防災研究所 矢守克也教授)
「日常的な経済・社会活動を行いながら、来るかもしれない災害に備える。この両立・バランスをどう取るかがカギになると思う」
参加した職員たちは、臨時情報が出たときどのような対応が求められるのか理解を深めていました。