「包括的性教育」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
「包括的性教育」とは、ユネスコが発表した「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に基づいて、身体や生殖の仕組みだけでなく、人間関係や性の多様性、ジェンダー平等など、自己決定能力などを含む人権尊重を基本とした性教育のことです。
宮崎市は、この「包括的性教育」を、21日、初めて保育施設で実施しました。
園児たちはどんなことを学んだのでしょうか。
宮崎市の小戸保育所で行われた「包括的性教育」には、4歳児と5歳児、あわせて25人が参加しました。
講師を務めたのは、県助産師会のメンバー3人。
まず、絵本を使って、赤ちゃんがどうやってお腹の中に入り、どのように成長するのかを紹介しました。
また、生まれる様子を人形を使って再現したり、赤ちゃんの成長に応じた大きさの人形を抱っこしたりしました。
そして、最後に「身体の命に係わる場所は大切にしましょう」と呼びかけました。
(園児)
「楽しかった」
「赤ちゃん(の人形)を抱っこするところが楽しかった。みんなの命の話しをした」
(宮崎市親子保健課 田村里美課長)
「性感染症ですとか、子宮頸がんり患とか、望まない妊娠が多かったりという背景の中で、幼児期からのこういう子どもの発達段階に応じた教育ができるというところは本当に今回いい機会だったなというふうに思っております」
宮崎市は、今年度、保育園や幼稚園など22か所で未就学児を対象にした「包括的性教育」を行うことにしています。
【包括的性教育とは】
ユネスコが発表した「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に基づいて、身体や生殖の仕組みだけでなく、人間関係や性の多様性、ジェンダー平等、自己決定能力などを含む人権尊重を基本とした性教育のことです。
学習目標が年齢別にまとめられていて、
(1)人間関係
(2)価値観、人権、文化、セクシュアリティ
(3)ジェンダーの理解
(4)暴力と安全確保
(5)健康とウェルビーイング(幸福)のためのスキル
(6)人間のからだと発達
(7)セクシュアリティと性的行動
(8)性と生殖に関する健康
これら8つの項目を繰り返し、継続的に学ぶことが勧められています。
全国のトップニュース
衆議院選挙・迫る投票日 各党の勢いは… “投票の判断”何を重視?終盤情勢が判明【news23】

【速報】トランプ大統領“3月19日に高市氏と日米首脳会談を予定” 衆議院選挙での高市総理と連立政権への支持表明も

【大雪情報】衆院選の投開票日に直撃へ 週末8日頃にかけ今季最強レベルの寒波が襲来 普段は雪の降らない九州・四国・近畿・東海・関東の太平洋側でも雪の可能性あり 大雪のシミュレーションで見る最新予想は?

柏崎刈羽原発6号機 週明け9日(月)にも再起動へ 1月21日に14年ぶり再起動も不具合示す「警報」で原子炉止める 東京電力

都内で相次いで億単位の現金狙われた事件 上野の事件で使用の“逃走ワゴン車”千葉→茨城→栃木→さいたま市へ… 実行役らの行方を追う 警視庁

「骨らしきものが見える、人の手も…」おたるドリームビーチの砂浜で男性の遺体発見 ほとんどが砂に埋まった状態 身分証明書も見つかる

米ロの核軍縮条約「新START」失効に中国外務省が「遺憾の意」 トランプ氏提唱の新たな核軍縮交渉には参加しない姿勢を強調

「モームリ」事件 弁護士ら3人を弁護士法違反の疑いで書類送検 労働組合への「賛助金」などという名目で「紹介料」受け取りか 組合の実態は 警視庁
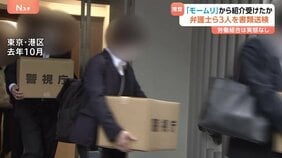
カテゴリ
Copyright © Miyazaki Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.