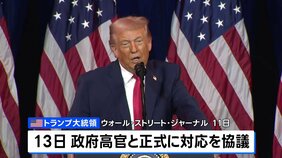今年は日本初の鉄道が新橋・横浜間に開業して150年の節目の年となりますが、地方の鉄道に目を向けると利用者の減少に伴う経営難など、その環境は厳しさを増しています。
過去の台風被害による廃止を乗り越え、観光資源として生まれ変わった「高千穂あまてらす鉄道」を通して、地方鉄道のこれからを考えます。
住民の足を支えた高千穂線・TR高千穂鉄道
秋の行楽シーズンを迎え、多くの観光客でにぎわう高千穂あまてらす鉄道。観光用の車両で大自然の中を走る人気の観光施設です。
(観光客)
「気持ちよかったね風が」
「歴史を感じるというか、いいなと思った」


1972年、高千穂線の延岡・高千穂間が全線開通。住民悲願の鉄道でした。
その17年後、JR九州から第3セクター「TR高千穂鉄道」が事業を引き継ぎ、住民の足を支えました。



しかし、2005年9月の台風14号により、鉄橋が2か所で流失するなど甚大な被害を受け、2008年に全線廃止。旧国鉄時代から続く73年の歴史に幕を下ろしました。


「高千穂あまてらす鉄道」の歩み
この時、線路跡地の活用に手をあげたのが、高千穂町出身で東京在住の作家、高山文彦さんです。
(高千穂あまてらす鉄道 高山文彦社長)
「(全線廃止から)なんとか15年やってきたんですよね」

高山さんは「高千穂あまてらす鉄道」を設立。
木製のトロッコを駅構内で走らせることからスタートしました。

その後、徐々に運行距離を延ばし、2010年には「トロッコカート」を高千穂駅から天岩戸駅まで運行。

さらに、2013年には高さ105メートルからの眺めが楽しめる「高千穂鉄橋」までの運行ができるようになりました。


今では、30人乗りの「グランド・スーパーカート」を導入し、人気を集めています。


あまてらす鉄道専務の齋藤拓由さんは、その魅力について・・・
(高千穂あまてらす鉄道 齋藤拓由専務)
「一番の売りですね、コミュニケーションなのかなと思ったりします」
高千穂鉄道の運転手を務めていた齋藤さんは、今後のあまてらす鉄道について次のように話します。
(高千穂あまてらす鉄道 齋藤拓由専務)
「鉄道が復活する時があると思うんで、そういうのを信じて、ずっと線路を守っていきたいと思います」