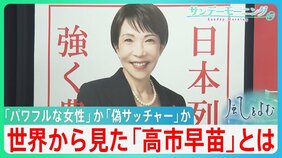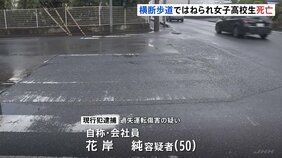南海トラフ巨大地震への備えです。
宮崎県沖に整備が進められている津波観測網「N-net」の沖合システムについて、防災科学技術研究所などは、来月1日から試験運用を開始すると発表しました。
「N-net」は、南海トラフ地震の想定震源域のうち、観測網が設置されていない高知県沖から日向灘の海底に整備が進められているもので、地震計や津波計などを備えた海底ケーブルを設置し、地震や津波の発生をいち早く検知するシステムです。

防災科学技術研究所と文科省は、沖合に位置するシステムと沿岸に位置するシステム、それぞれで敷設工事を実施してきましたが、「沖合システム」について、来月1日から試験運用を開始すると発表しました。
この整備により、地震は最大20秒ほど早く、津波は最大20分ほど早く検知できるようになるということです。

また、今年の秋には、試験運用を終えて本格的に運用を開始し、防災科研はホームページに観測データを公開するほか、データを気象庁にも提供し、緊急地震速報や津波情報に活用するということです。

(スタジオ)
改めて、「N-net」とはどのようなシステムなのでしょうか。

今回、試験運用が始まる「沖合システム」ですが、沖合側のケーブルは串間市と高知県の通信施設を接続していて、その長さはおよそ900キロにわたり、地震による揺れや津波を観測する装置が18台設置されています。
この装置で観測されたデータは、ケーブルで串間市と高知県の陸上局に伝送され、防災科研のデータセンターなどに届きます。
これにより、地震の揺れや津波を今までより早く、直接検知できる仕組みとなっています。
こうした観測網は、ほかの南海トラフ震源域では整備されており、今回、「N-net」の完成により、南海トラフ震源域での空白域がなくなります。
沿岸システムも今年度中に整備が完了する予定で、今後、観測データにより、地震や津波のメカニズムの解明など、様々な防災科学技術の発展が期待されているということです。