行き過ぎた校則、いわゆる「ブラック校則」についてです。
宮崎県弁護士会は、去年、校則に関するアンケート調査を実施し、その結果を踏まえ、校則の見直しをさらに進めるよう県内の学校や教育委員会に提言しました。
県弁護士会は、全国的な校則見直しの動きを受け、去年9月、全県立高校とすべての宮崎市立の中学校に校則の見直し状況についてアンケート調査を実施しました。
そして、先月、その結果を踏まえて、県内の教育委員会や学校に、校則の見直しをさらに進めるよう提言したということです。
(宮崎県弁護士会 成見暁子弁護士)
「個性や多様性、主体性が尊重される国際化の時代にふさわしい校則へ、宮崎県内の学校がさらに見直しを進めることを期待をして、今回の提言をまとめさせていただきました」
県弁護士会のアンケートによりますと、2021年1月から、去年6月までに、ほとんどの学校で校則の見直しや改正が実施されたということです。
ただ、県弁護士会ではジェンダーや多様性などの観点から「校則の見直しはいまだ途上にある」と指摘。
例えば、下着については県立高校で17校、中学校で20校が何らかの規制があると回答し、具体的には色や柄に関して規定が設けられています。
一方、制服についてはここ数年、性別に関係なくスカートやスラックスなどを選択できるよう制度の導入が進められていますが、県立高校では18校、中学校で11校、男女別に制服が定められているということです。
(宮崎県弁護士会 成見暁子弁護士)
「子どもの自己決定権をはじめとする、さまざまな重要な人権や権利を、校則が一律に制限するというものですから、それが許されるのかどうかということについては厳格に審査をされるべきだと考えます」
県弁護士会では、「校則による子どもの人権や権利の制限は、最低限に絞ることが望ましい」などとして、学校側に校則見直しについて継続的に取り組むよう求めています。
(スタジオ)
見直しは少なからず、ほとんどの学校で進んでいるということですが、学校側からは
「生徒と学校の解釈のズレがあり指導が難しくなっている」
「今あるルールを守る意識の低下がある」
などという声も挙がっているということです。
社会全体で校則の見直しについて考える必要がありそうです。
全国のトップニュース
トランプ大統領 グリーンランド領有めぐり同調しないヨーロッパ8か国に10%関税 各国から反発の声
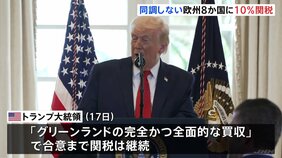
アパートに女性の遺体 警察 殺人放火事件と断定 捜査本部設置 愛知・豊田市
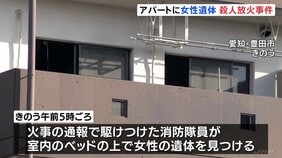
ぎりぎりまで資料に目を通す受験生たち 「大学入学共通テスト」2日目始まる きょうは「理科」「数学」「情報」
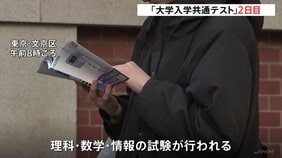
静岡・藤枝市の山林火災 現在も延焼中 ヘリコプターなどによる消火活動続く

「頭が真っ白になり怖くなってしまった」76歳の女性をひき逃げか 29歳の男を逮捕 千葉・旭市

大阪ダブル選 自民党大阪府連、候補者擁立見送り 「お付き合いする必要がない選挙だなと」自民大阪府連・松川るい会長

1時間で6件の連続不審火 放火の可能性 いずれの現場も火の気なし 栃木・宇都宮市

「震災がなければ…」死者6434人に含まれない「遠因死」 知られざる遺族の悲しみ 阪神・淡路大震災31年【報道特集】

カテゴリ
Copyright © Miyazaki Broadcasting Co.,Ltd. All rights reserved.