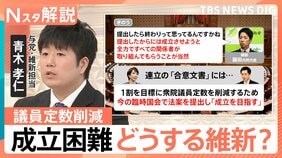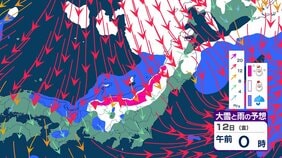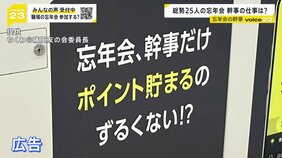息の合ったダイナミックな踊りを披露するのは、岩手県立岩泉高校の郷土芸能同好会の生徒たちです。
演目は「中野七頭舞(なかのななずまい)」。岩泉町の小本地区に古くから伝わる踊りで、江戸時代に起きた大飢饉の際に創作されたと言われています。
踊りは原野を開拓して田畑を作り、収穫の喜びを分かち合うまでの流れを表現しています。
踊り手の役割も、土地を測量する「先打ち」、測量を基に土地を改良していく「谷地払い」など原野の開拓をイメージした「7つ」に分かれています。それが「七頭舞」の名前の由来と言われています。

一番激しい演舞とされる「ツゥトウツゥ」です。中野七頭舞の中でも一番盛り上がる踊りとされていて、全身を使って舞うため生徒たちも踊りが終わると息が上がります。

(岩泉高校郷土芸能同好会 坂下雄斗 会長)
「中学校のころに町の芸能祭で中野七頭舞を見て、自分もこうやって地域の方々を元気づけられるように踊りたいと思って入会しました」
メンバーをまとめるのは、会長の坂下雄斗さんです。北海道出身の坂下さんは、岩泉中学校に転校してきたことで「中野七頭舞」に出合いました。
踊りの役割はもちろん、仲間を導く「先打ち」です。
同好会の練習は週に3回。ほとんどの生徒がバスケットボールや弓道、吹奏楽などの部活動との掛け持ちで参加しています。メンバーの中にはきょうだいの影響で入会した生徒もいます。