東京電力柏崎刈羽原発を巡っては、新潟県独自の3つの検証の一つ『事故が起きた際の避難』について検証委員会がおよそ5年をかけて議論し、456の論点を取りまとめました。
避難検証委員会の委員から話を聞き、残された課題などをシリーズでお伝えします。
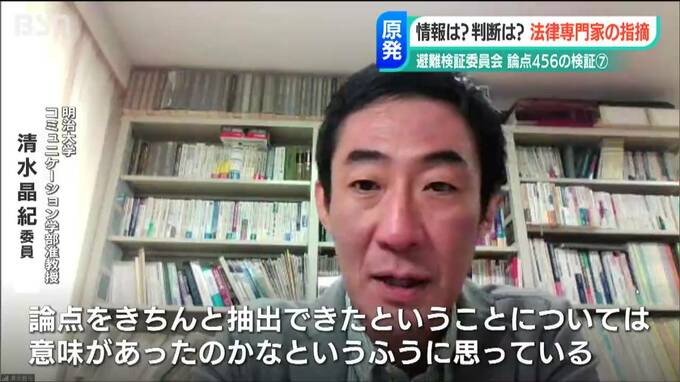
今回話を聞いたのは、行政法や環境法を専門とする明治大学情報コミュニケーション学部准教授の清水晶紀委員です。
【清水晶紀委員】
「一つ一つの論点をですねきちんと検討してまとめられるところは総意としてまとめられるように何とか持っていって論点をきちんと抽出できたということについては意味があったのかなというふうに思っています。一方で、それぞれの個別の論点を掘り下げていくとどうしてもその専門的な知見がもっとある方に検証していただく必要がある部分ってのはたくさん出てくるってところがありますので、そこの部分をきちんと県の側で受け止めていただいて、実効性の確認向上っていうことを進めていって欲しいなということはすごく強く思っているところです。」
清水委員が挙げる課題、それは「避難に関する情報」についてです。
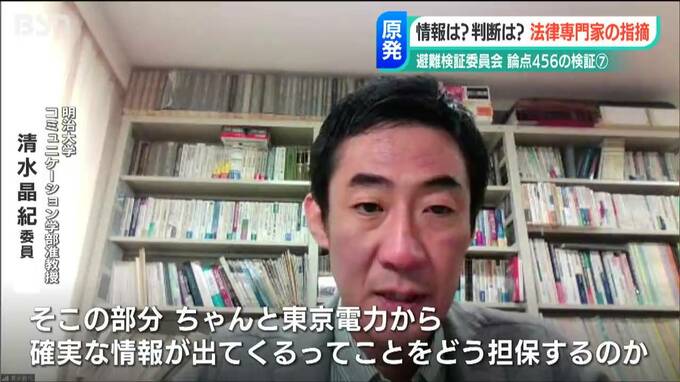
【清水晶紀委員】
「やっぱり情報をどうきちんと共有していくかっていうところですね。この委員会の序盤のところで特に集中的に議論したところであるんですけど、やはり東京電力からきちんとした情報が出てこないと全て動きをスタートできないので、そこの部分ちゃんと東京電力から確実な情報が出てくるってことをどう担保するのか。東京電力はこの数年間の間にも大問題が出てきてしまっているっていうところはあるので、確実にちゃんとした情報が出てくるだろうっていうだけの信頼性はやっぱり今の段階ではない部分もあると思うんですね。そこはやはり東電自身もきちんといろいろ努力しているとは思いますけど、ブラッシュアップをしていって頂きたいなってことは非常に強く思います。」
そして東京電力から得た専門的な情報をどう自治体側が消化し、どう分かりやすく住民に伝えるかも課題となっています。
【清水晶紀委員】
「東電から出てくる情報って非常に技術的な難しい情報になってくるので、それを自治体とか国側は受け止めることになるわけです。とりわけ市町村レベルとかになるときちんとその情報を理解できる、受け止めきれるかっていう問題ももちろん出てくると思うので、その辺り東電は『リエゾン』っていう専門の方を派遣して対応するみたいなことも言ってましたけども、そういうところも、もう少し詰めて考えるってことは重要なのかなと思っています。」

また安定ヨウ素剤の服用を巡っては得られた情報に基づき、誰が判断するかという点でも課題が残されています。甲状腺の被ばくを避けるための安定ヨウ素剤は被ばくが始まると予想される24時間前から被ばく後2時間までに飲むことで効果を発揮するとされています。国や県・市町村から指示があった場合に服用することになっていますが福島第一原発の事故では国や県は指示を出さず、市町村がそれぞれ独自に判断をしました。検証委員会が内閣府にヒアリングしたところ内閣府は「服用のタイミングは容易には示せない」と回答しています。

【清水晶紀委員】
「ヨウ素剤の服用についても最終的に誰が責任を持って飲んでくださいという指示をするのか。ということが法制度上もはっきり明確には書いてない部分があったりして、そういうところをどういうふうに考えていくのかっていうのはやっぱり実際に事故が起きたときに一番重要なポイントになると思うので、意思決定のあり方というところはもう少し詰めて考える必要があるかなというふうに思っています。」
また、清水委員が『実効性ある避難計画』にするために議論すべきだと考えているのが被ばくの許容量についてです。一般の人が平常時に受ける放射線量の限度は年間1ミリシーベルトまでという国際基準がありますが清水委員は、緊急時にはどこまでの被ばくを許容すべきなのか県が県民に対ししっかりと説明するべきだとしています。
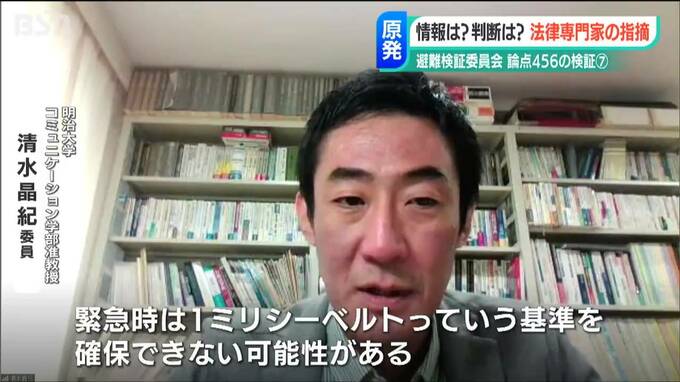
【清水晶紀委員】
「緊急時については特にそういう基準が法律上はないんですね。そうなったときに、じゃあ1ミリシーベルトってところに立ち戻って考えるっていうのは一つの立場とは思うんですが、やっぱり緊急時っていうのは1ミリシーベルトっていう基準を確保できない可能性がある。だからこそ避難しなきゃいけないっていう話になるので、そういう意味では1ミリシーベルトっていうところにこだわる必要は、私はないのかなというふうに思っています。ただ、どこまで許容するんだっていうことについては、いろいろ議論があり得ると思うんですが。そのときに県としては、例えば『5ミリシーベルト』っていう基準が放射線管理区域ってレントゲンとか撮る作業に従事されている方の基準がありますけど、そこまでになんとか抑える形の計画を作りましたと。だから皆さんこの計画で実効性があるっていうふうに検討して考えてますっていう形で説明をされるのは、例えば一つの方法としてはあると思うんです。そういう形で何らかの根拠を持って県民に対して県民がきちんと安心できるような説明をするっていうことが求められるのかなというふうには思います。」














