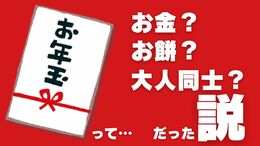戦後の殺伐とした世相の中、東大の学生だった山崎晃嗣(死亡時27歳)は「必ず儲かる」と出資者からカネを集め、それを「高利貸し」として運用しました。最初のうちこそうまくいった山崎でしたが、やがて悲劇的な最期を迎えることになります。三島由紀夫『青の時代』高木彬光『白昼の死角』のモデルになった事件です。(アーカイブマネジメント部 疋田 智)*文中敬称略
戦後の低金利時代に
太平洋戦争が終わってまだ3年しか経っていない1948年のこと、東大の現役学生だった山崎晃嗣は、友人の医大生らとともに貸金業「光クラブ」を設立しました。
山崎は「年利18%で、黙っていても儲かる」と出資者を募り、「現役東大生が貸金業」という話題性から、多くの出資者を集めました。
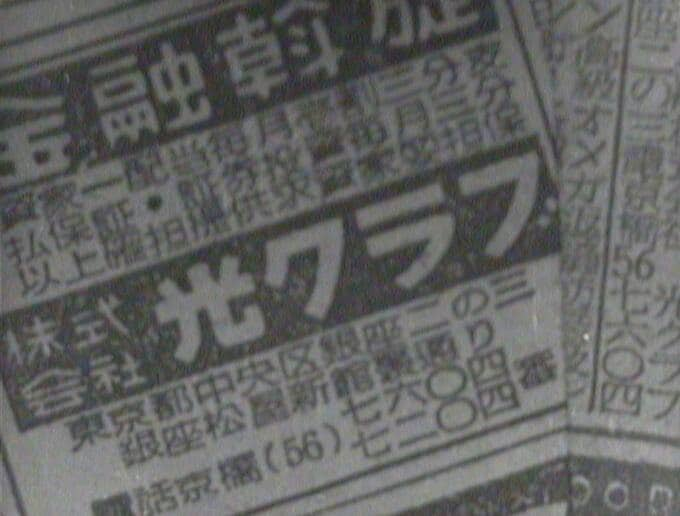
ここには、当時の低金利が、大いにモノを言ったといいます。
戦後、GHQの統制(ドッジ・ライン)のもと、当時の銀行金利は年利1.83%にしかならず、戦後の小金持ちたちは、資金の出しどころに苦労していたのです。
「学生起業」の元祖?
山崎は、スリムで端正なルックスを持っていました。会社の名前も「光クラブ」とハイカラでした。
学生社長が、メガネにスーツ服で営業する姿は、ちまたで大いに話題になりました。
怪しげな金融業者と異なり、清潔で知的、スマートなイメージに見えたといいます。
いわば「学生起業の元祖」です。

一方、借りる客にも事欠きませんでした。
銀行の貸し渋りで運転資金の調達に苦労する中小企業の注目を浴び、本社の前は高利にもかかわらず借りたい客が列をなしたと言います。
そう考えると「商工ローンの元祖」といえるかも知れません。
「アプレゲール」と呼ばれて
光クラブは、会社を立ち上げてわずか3か月で1000万円を集めました。これは現在の価値にすると約10億円にもなります。4か月後の1949年(昭和24年)初頭には株式会社とし、本社を銀座の一等地に移転しました。

山崎は光クラブを資本金400万円、社員30人を擁する会社にまで成長させました。
一方、山崎はプライベートも派手で「オンナは道具」と公言し、盛んに女遊びを繰り返し、「ドライな付き合い」を続けたといいます。
こうしたライフスタイルは「アプレゲール(=戦後派。それまでの道徳にとらわれずに行動する若い人々のこと)」と言われ、山崎はその代表とされたのです。