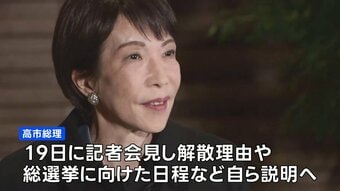最大震度7を観測した能登半島地震の地震活動によって、石川県の輪島市内を流れる町野川の支流の河川では、崩れ落ちた土砂で川が複数か所でせき止められている可能性が高いことがわかりました。分析を行った京都大学防災研究所の研究者は、今後の雨によって土石流が発生し、下流で被害が出る可能性があると指摘しています。
京都大学防災研究所の松四雄騎教授は、国土地理院が公開している能登半島地震発生の翌日(2日)に撮影された衛星写真をもとに、土砂が崩落した状況などを解析しました。その結果、輪島市町野町を流れる町野川の支流の河川では、地震によって崩れ落ちた土砂が川の通り道を塞ぐ「河道閉塞」が複数起き、川をせき止める「震災ダム」ができている可能性が高いということです。
松四教授によりますと、これらの「震災ダム」は大規模なものではないものの、一部は傾斜が急で、しかも大量の土砂が堆積している状態のため、今後の雨などによって壊れたり、水が溢れたりした場合には土石流が発生し、下流で被害が出る可能性があるということです。
松四教授は河川の水位が長時間減少したり、急に上昇したりしないか注意するとともに、水や土砂の急激な流出に警戒が必要だとしています。
注目の記事
歩行者が消えた⋯ハイビームでも「見えない!」 夜の運転に潜む恐怖現象と“罠”⋯対策は?県警の実験で検証

“車版”モバイルバッテリーが救世主に?! バッテリー上がりにジャンプスターターが活躍 スマホ充電が可能な商品も 車のプロに“冬の運転”聞いてみた

久米宏さん「殺されてもいい覚悟」と居酒屋で学生と「ピッタシカンカン!」の素顔 落語家・林家彦いちさんに聞く『久米宏、ラジオなんですけど』TBSラジオで15年共演

南鳥島沖だけではない、日本の山に眠る「レアアース」 新鉱物が問う“資源大国”の夢と現実「技術革新がないと、資源化できる規模の採掘は見込めない」愛媛

「許せない、真実を知りたい」 中古ランドクルーザー480万円で購入も 未納車のまま販売店倒産へ 全国42人同様の被害訴え 店側の弁護士は「納車困難なのに注文受けていたわけでない」

"理想の条件"で選んだ夫が消えた…27歳女性が落ちたタイパ重視の「恋の罠」 20代の5人に1人が使うマッチングアプリ【前編】