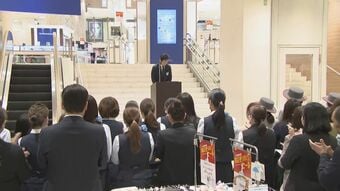地域の心のよりどころとなっている「神社」。そんな神様にお仕えする「宮司」が深刻な人で不足に陥っています。
そんな中で、地域の神社を支えるため、一人で12社を掛け持ちする女性宮司がいます。神社から神社へ飛び回る女性宮司の、多忙な日々に密着しました。
きっかけは巫女のバイト、突如降りかかった責任に涙も…

愛知県田原市の八柱(やはしら)神社は、創建から800年余りと、長きにわたり住民の心のよりどころとなってきた氏神様です。
大森愛子さん(53歳)は、20年ほど前からこの神社の宮司を務めています。この日は実りの秋に感謝をする大祭を執り行う日でした。
神事を終えた大森さんは、着替えもせずそのまま車に乗り込みます。
(大森愛子さん)
「まだ、きょうやらないといけないことがある。猿田彦神社に移動して…」
5分ほど行ったところで車から降り、頭の飾りをつけて山道を登ることさらに5分。
訪れたのは、創建から350年以上とこちらも歴史ある猿田彦神社です。今は氏子がたった15軒。猿田彦神社もこの日が大祭の日でした。
大森さんは、無事務めを終えた後、氏子との会食で用意されたお弁当に箸をつけず、また車を走らせます。
(大森愛子さん)
「どうやって地域と氏子を守ろうかと思うと、何かやらずにはいられなくなる」
大森さんが神職に関わるようになったのは、20歳の頃。きっかけは、衣装に憧れて始めた巫女のアルバイトでした。
それをしばらく続けていると、宮司の資格を取るよう頼まれたのです。
その後、先代が病気で引退すると共に宮司を引き受ける事に。
(大森愛子さん)
「自分より上座に座る人がいなくなって、(責任が)重いどころじゃない。最初は泣いてばかりでしたね」
いきなり責任重大になった大森さん。実は先代から引き継いだ神社は、7つ。一気に7社の宮司になったのでした。
渥美半島には常勤の宮司がおらず、慢性的に人手が不足していたためです。