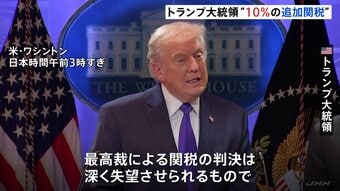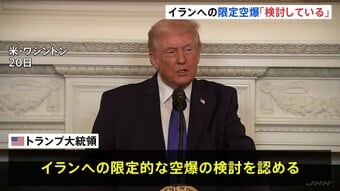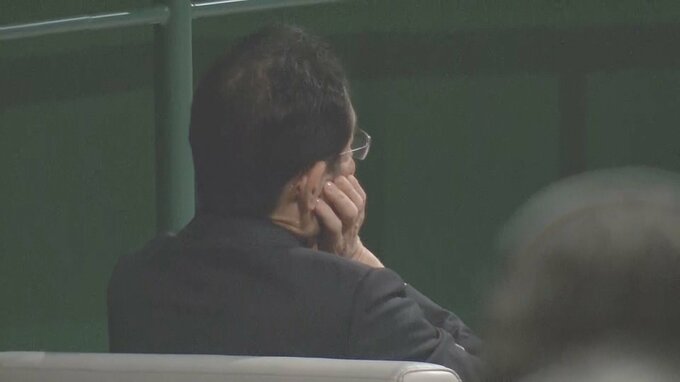
「戦闘再開」の一報を受けて、ドバイに滞在中の各国が慌ただしく動いた。当初、岸田総理はホスト国であるUAEとの首脳会談を予定していたが、先方から直前にキャンセルされた。他にも、欧州の国との首脳会談がキャンセルされたり、時間が大幅にずれて電話のみの会談になったりした。
ただ、イランーーハマスに影響力を持ち、イスラエルと敵対するこの大国とは、日本側から要請し、急きょ電話会談が行われたことには、日本ならではの存在感を示そうと奔走した形跡が窺える。岸田総理は、ドバイ滞在中の2日間で、9つの国と地域の指導者と会談した。
結果的には、日イスラエル首脳会談中にディールが崩れたことになる。これは決して「日本が軽視されている」という単純な話ではない。日本側も、この会談で事態が劇的に好転するという甘い期待は抱いていなかったはずだ。それでも、「双方と話ができる日本」がどこまで影響力を発揮できたかには疑問符がつく。
中東地域に詳しいある専門家は、今の状況を格闘技に見立て、「ネタニヤフ首相が顔を真っ赤にして技をかけている状態。レフェリーのアメリカにさえ止められない。日本には無理。リングサイドで見守ることしかできない」と冷静に突き放した。
今後、事態の収束に向けて日本としてできることはあるのか。
この問いを外務省高官にぶつけると、「何ができるかと言われると難しい。関係国との対話と、周辺国を含めた支援を地道に続けるしかない」と語る。一筋縄ではいかないこの問題の解決には、誰も“特効薬”を持ち合わせていない。日本外交にできること、その模索が続く。