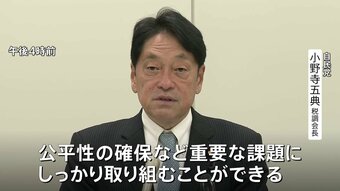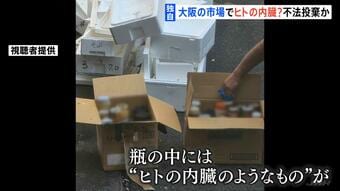実践/大人の介入を減らそう! NGワードは「ダメ」

あそび大学の入り口には「大人、口出すべからず」と書いてある。保護者はあそび場に入れない。大人が子どものあそびに介入するのをできるだけ減らすことが狙いだ。
あそび場にはスタッフの大人がいる。しかし、子どもがけがをしないよう配慮はするが、基本的に見守るだけ。そして、子どもの“やりたい気持ち”を邪魔する言葉は使わないようにしている。
●「ダメ」など“否定”はしない
●「何も作らないの?」など“目的”を求めない
●「綺麗にできたね」など“評価”はしない
時には絵の具を何本もニュルニュル絞り出す子もいるが、大人は「もったいない」とは言わない。容器に穴を開けようと2時間奮闘する子がいても、とりあえず見守る。

共同主催の中山さんは、教え、導くのも大人の役割ではあるが、大切なのは子どもが失敗を恐れず自分の頭で考えることだと話す。
Chance For All 中山勇魚 代表理事
「今の日本の教育ってずっと『大人の言う通りにしろ』と我慢させ続けるのに、社会人になった途端『自分の頭で考えろ』と言われる。そんなのおかしいですよね。だから、ここでは全力で遊ぶ中で子ども自身が考えること、失敗や経験を尊重しています」
参加した子からは
「自分で何つくるか決められて楽しい!」
「ゲームの楽しさとは違う楽しさ」
「やりたいことやれてスッキリした」
など、いつもと違うあそび場を満喫している様子がうかがえた。

未来/持続可能で豊かな“あそび”ある社会を目指して
初開催から2年近く経ち、リピーターの子が初参加の子の世話をすることも増えた。学年も学校も違う初対面の小学生たちが助け合う姿は微笑ましいと、スタッフたちは嬉しそうに話す。

子どもたちは、あそび大学でたくさんの挑戦と失敗を経験しながら成長していく。絵の具を出しまくった子は、大人になったらどのように振り返るだろうか。
あそびに正解も不正解もないだろう。
子どもが夢中になるあそびはたくさんあるが、「子ども自身がゼロからやり方を考えるあそび」も選択肢の1つとして単純に楽しそうだと感じた。あそび大学に通わなくても、家でもできることもあるのかもしれない。
大切なのは大人は見守りに徹すること。
そう「大人、口出すべからず」だ。