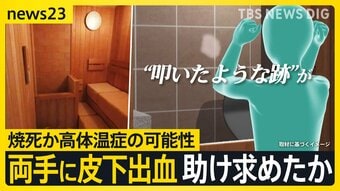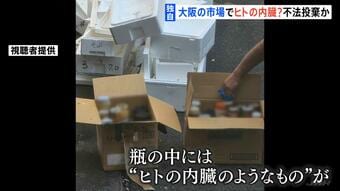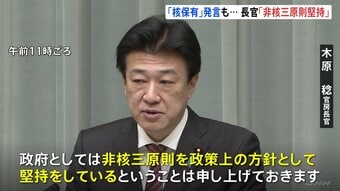マニュアルがあるゲームやおもちゃで遊ぶのは得意だけど、自分でゼロから考えて遊ぶのは苦手…という子が増えているらしい。そんな今どきの小学生が自由に遊ぶ、ちょっと変わった“あそび場”がある。キーワードは「大人、口出すべからず」だ。
自由/毎月1回 無料開放 子どもだらけの「あそび大学」
とある日曜日、小学校の教室の3倍はある空間…棚には地域の町工場から提供された不揃いの布や和紙、床にはウレタンや木材が置かれている。
ここは千葉大学・墨田サテライトキャンパス(東京・墨田区)の工房。毎月1回、小学生を対象に無料で解放している「あそび大学」の会場だ。

集まったのは小学生180人ほど。みんな楽しそうに何か作っているが、よく見ると、素材を投げ合って遊ぶ子や学生スタッフと話すだけの子、外遊びのスペースでキャーキャー走り回る子もいる。
「何でやっていることがバラバラなの?」
こんな疑問を持つ人もいるかもしれないが、あそび大学は“何をしても、しなくてもいい”自由な空間だ。なぜ自由に重きを置くのか。そこには昨今の子どもの遊び方への問題意識がある。

現状/だんだん増えている「自由に遊ぶこと」が苦手な子
Chance For All(あそび大学・共同主催)が運営する学童の職員たちは、ここ数年、自由に遊べない子が増えていると感じていた。
【お絵かき】「目はこれでいい?」「耳は?手は?足は?」といちいち確認して、「いいよ」と言われないと続きを描かない子
【紙飛行機】「遠くに飛ばしたい」と言うわりに自分であれこれ試さず、すぐ正解の作り方を聞きたがる子
せっかくのあそびの時間なのに、誰かの許可や決まった手順がないと安心して遊べないのだ。
なぜなのか。
あそび大学共同主催の千葉大学デザインコース・原教授は背景に大人の存在があると指摘する。
千葉大学 原寛道教授(環境デザイン研究室)
「今の社会では、効率的であることが強調されすぎていると思います。そのため、大人があそびに意味づけをしたり、制限を加えたり、失敗する前に止めたり…子どものあそびに大人が侵食しています」
つまり、大人が関わりすぎて、子どもは大人の顔色をうかがいながら遊ぶことが多くなっているというのだ。
では、そんな子どもたちにあそび大学では“あそび”をどのように提供しているのだろうか?