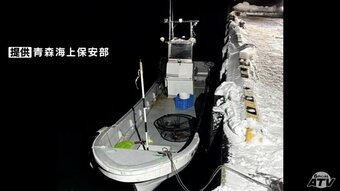「アキアカネ」減少の原因は…「2000年代の一部の殺虫剤散布」と「水田の減少」?

こうしたアキアカネの減少は全国で起きていて、この問題を研究している石川県立大学の上田哲行名誉教授は2000年代の減少は当時普及した一部の殺虫剤が水田に散布されるようになったことが大きな要因と見ています。さらに時代の流れとともに産卵場所であった水田自体も減っていき、トンボの生息環境は年々厳しくなっています。
青森県トンボ研究会 奈良岡弘治さん
「アキアカネ、ナツアカネ、ミヤマアカネは田んぼに卵を産んで幼虫が育っているから、水が汚れて住めなくなると減ります」

こうした現状に危機感を覚えた奈良岡さんは自然環境を守るための事業にも携わってきました。それが弘前市と市民グループが2003年に完成させた「だんぶり池」です。休耕田を整備しトンボが生育しやすい湿原に生まれ変わらせました。いまも生き物の観察会が定期的に行われていて子供たちには貴重な学びの場です。こうした取り組みを通してトンボを守ることの意義を奈良岡さんはこう強調します。

青森県トンボ研究会 奈良岡弘治さん
「トンボを見て、トンボがいっぱいいればここの自然は非常に人間が住みやすいきれいな自然だとわかる。その目安となると思う。だから、いっぱいトンボがいればいいなと思う」
失われつつある童謡「赤とんぼ」で描かれた情景。これを子供たちに引き継ぐことができるのか。いまが、大きな岐路となっています。

赤トンボを研究している上田教授によりますと2000年代に一部の殺虫剤で数は減りましたが、石川県や富山県では近年その殺虫剤の使用量が減った結果、少しずつですが数は回復しているということです。トンボは環境の良さを示す1つの指標と言われています。その保全は身近なところから地域の環境全体を考えるきっかけになるかもしれません。