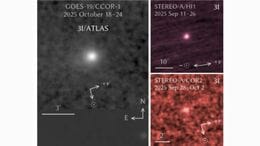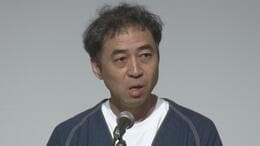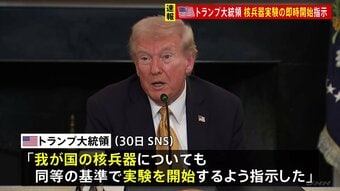フリージャーナリスト 浜田敬子氏:
水道事業は各自治体がやっていますが、コスト削減のために人員を削減している。人員を削減したから老朽化の手当ができていない側面もあるという記事を先日読んだので、悪循環ですよね。
小川彩佳キャスター:
この人口減少や老朽化は“見えていた未来”でもあったわけです。それをここまで先延ばしにしてきたこともあるのかなとも思うのですが。
東京大学准教授 斎藤幸平氏:
水道システム自体ができたのは高度経済成長の時代なので、そのときは人口も増えて人々が水を使うようになるという楽観的な状況のもとで作ってしまった。現在は過剰投資の状態で、稼働率も6割ぐらいなので、そのあたりを見直していく必要が出てきているのではないでしょうか。
片山記者:
人口減少を自治体が直視していたのかは少し疑問で、産業の活性化や企業誘致などで一定の需要があるのでは?という見込みを立てていたところもあるようです。
もう1つは、水道行政を担当している人は人口も減っているので値上げしなければならないのを分かっているのですが、市長が値上げを判断するのに相当ハードルがあったようです。
小川キャスター:
民営化という選択肢はあるのでしょうか。
斎藤氏:
「公」に任せておくと効率が悪いので民営化してコストダウンしようという話になるんですが、むしろ海外では民営化をした結果「やっぱりうまくいかない」ということで再公営化をする都市がかなり増えてきています。
何が起きているかというと、コストダウンしようとすると一番手っ取り早いのは、専門知を持った職員の削減、あるいは利益を上げるために水道の値段を上げることがむしろ加速してしまいます。水のメンテナンスをする人もいなくなり、水質が安全ではなくなることも起きています。
一番有名なパリでは、25年の契約後に再公営化して、市民が参加する形で公的企業が建て直す形になっているんです。