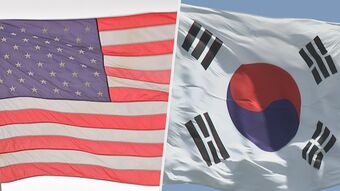21年東京五輪、22年世界陸上オレゴン大会と、最後までバトンがつながらなかった日本の男子4×100mリレー。世界陸上ブダペスト大会8日目の同種目決勝では、坂井隆一郎(25、大阪ガス)、栁田大輝(20、東洋大2年)、小池祐貴(28、住友電工)、サニブラウン・アブデル・ハキーム(24、東レ)のオーダーで37秒83の5位。3位のジャマイカとは0.07秒差だった。今大会では4年ぶりにサニブラウンも出場。メダル常連国に復帰するための再スタートを切った。
世界トップ選手たちとの差を痛感した2走の栁田
トラック&フィールド種目の日本勢最後の出場は、男子4×100mリレーだった。7月のダイヤモンドリーグ(以下DL)に37秒80の今季世界最高タイで優勝。メダルの期待もあったのは事実だが、現実は厳しかった。世界陸上予選で37秒71にタイムを縮め、決勝でも37秒83で走ったが、メダル獲得には37秒76が必要だった。1走の坂井は自身の走りを次のように振り返った。
「スタートはうまく切れて、カーブもしっかり伸びたと思います。しかし内側の米国の追い上げ、詰められている感じはありました。個人の力の差が出たな、それを痛感させられたな、というレースでした」
予選の区間タイムは10秒50(主催者発表)で、過去の日本選手と比べても良くない。風向きも影響するので単純に比較できないが、米国1走のC.コールマン(27、19年世界陸上ドーハ100m金メダリスト)が10秒41なので、坂井も悪くはなかった。
だが決勝は、タイムは発表されていないが、終盤は明らかに差を詰められていた。坂井は優勝した日本選手権後にケガがあり、練習が十分できない期間が生じていた。その影響がやはり出てしまったようだ。2走とのバトンパスに関しても「少し詰まり気味というか、攻めきれなかった印象があります」と、ロスが生じたことを反省している。
2走の栁田は予選で9秒02の区間タイムで走った。決勝は発表されていないが、同等のタイムで走ったと思われる。それでも前回オレゴン大会100m金メダリストのF.カーリー(28、アメリカ)や、今大会100m銅メダルのZ.ヒューズ(28、イギリス)、同4位のO.セヴィール(22、ジャマイカ)には引き離されたように見えた。
「各国の速い選手が2走に集まってくるので、僕のところでもっと前に展開しないとメダルは見えてきません。もっと力をつけないといけないな、と感じました。(予選の)バトンの区間タイムは日本選手歴代の中では速いと言っていただきましたが、決勝で勝負して離されたら意味がありません」
日本の1、2走は今できる100%の走りはしたが、準備不足などもあり、世界との差を見せつけられる結果となった。
3走の小池が接触して走りに影響か?
日本の3走は過去、桐生祥秀(27、日本生命)がリオ五輪で区間最高タイムで走ったこともある。メダル争いを確実にするなど、大きな役割を果たしてきた走順だ。今回は9秒台ランナー(19年に9秒98)の小池がその役割を担った。DLロンドンでも4走の上山紘輝(24、住友電工)に、「ここしかない」(江里口匡史コーチ)というタイミングでバトンを渡すなど、3走のスキルは高い。
「(内側のレーンの選手と)接触があって100%では走れませんでした。僕は2回くらいぶつかった印象でしたけど、頭が真っ白で走っている最中のことなので、走り終わってから“なんかぶつかったな”という感じで。持ち直して4(4走か、37秒4か)は届かせようと思ったのですが、無理に立て直そうと力が入った分、最後の10mはちょっと落ちたと思います」
小池の最後のスピードが落ちたことも関係したのだろう。4走のサニブラウンは加速を少し緩める走りになった。渡るかどうかぎりぎりのバトンパスになったが、DLロンドンと同じように、小池が相手の手の位置を正確に見極めてバトンを押し込んだ。そして4走のサニブラウンは、次のように振り返った。
「もらうところで振り返ったので、加速はあまりできない状態でやっていたかな、と思います。加速に乗れていなかったので、(メダルまでは)たぶん、無理でしたね。しかし日本も、ちゃんと走ればメダルは取れると思います。個人個人しっかり走って、バトンをしっかりつなげれば、というところにいると思います」
本人が話したように、決勝のサニブラウンは4位のイギリス、3位のジャマイカにまで届く勢いはなかったかもしれない。しかし予選では8秒93の区間タイムで走った。予選1組では最高タイムで、100m世界6位のスピードを存分に見せつけた。サニブラウンは今後も、日本の4×100mリレー最大の武器になる。
日本の伝統も大きな力に
08年北京五輪で銀メダル。初めてメダルを獲得した日本は、16年リオ五輪でも銀メダル。17年世界陸上ロンドンでは銅メダル、19年世界陸上ドーハでも銅メダル。メダル常連国となったが、それを可能にしたのは走力プラス“チームワーク”だった。
とにかくコミュニケーションを日頃からしっかり行う。食事に行くときなど、極力一緒に行動する。日常生活からお互いに話しやすい雰囲気を作っておけば、バトンパスの技術など細かい部分を気兼ねなく話し合うことができる。今大会では35歳と若いスタッフの江里口さんが、選手間のコミュニケーションをスムーズにする役割を担ったが、選手では最年長の小池が自然とリーダーシップをとっているようだった。
「日本のリレーは和を重んじるところがあります。僕以外の3名が個人種目(100m)を終わった後、和やかな感じで、まとまっての行動ができたと思います」
失敗したときに「この人はどう思うんだろう」というような疑心が生じたら、思い切ったバトンパスはできない。その点、ブダペストの4×100mリレーチームは、良い関係を築けていた。結果として完璧にはできなかったが、良い関係がバトンパスにも現れていた。
「リレーは後ろの走者がバトンを必ず渡してくれる、届かせてくれると信じて、前だけ見て走ります。そういう信頼がなければいけないので、一発目(初めて)のメンバーで全員、前だけ見て、全力で出られていたので、来年以降に向けては非常にいいことだったと思います」
リオ五輪で銀メダルを取り、金メダルを目標にした東京五輪は残念ながら決勝で途中棄権に終わった。翌年の世界陸上オレゴンでは失格し、今大会が再生に向けて第一歩を踏み出した形になる。そこで改めて、日本の4×100 mリレーの伝統は精神的な部分を中心に根付いていることを示した。来年以降の世界大会ではまた、日本がメダル候補に戻る。
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)