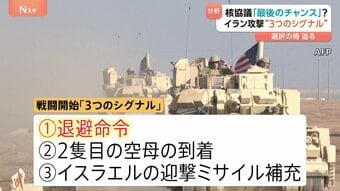グランドの標語「もう一超」 その意味は?

小笠原キャスター:
慶應高校のモットーは「エンジョイベースボール」です。例えば、▼髪型は自由、▼選手の主体性を伸ばす、▼「監督」ではなく「森林さん」呼び。
この“主体性を伸ばす”ということで言うと、グランドには「もう一超(いっちょう)」という標語があるんだそう。「いっちょう」は“一丁”ではなく“一超”と書きます。
監督に意味を聞いたところ…
森林監督:
「今まで通りの取り組みだと、今まで通りの結果に終わる。自分もチームも、今までの自分を少しずつ超えようという意味だと選手に教えてもらいました」
実はこの標語は、選手たちが考えて自主的に掲げたものだということです。
そして森林監督は、2年前に高校野球部のWebサイトの動画でこのようなことを言っていました。
「“こういう高校野球もあるんだ”と示していくのが慶応の役割。結果を出すことで説得力が出てくる。慶応のスタイルを続けながら日本一を目指す」
ホラン千秋キャスター:
本当に、生徒の皆さんにとっても大変大きい存在だったんだろうな、というところが伝わってきますけれども。何か関係性で感じるところはありますでしょうか?
スポーツ心理学者(博士) 田中ウルヴェ京さん:
「もう一超」っていう言葉は、どのスポーツでも必要なことなんですけど、その「もう一超」とはつまり、“どこまでも”なんですよね。今日の限界がどこかわからないので、「もう一超」って言いながら、「どこまでが限界なんだ」と自分で思いながら、そのエネルギーが出るときってやっぱり“主体性”なんですよね。
その主体性って何かっていうと、「なぜ今この練習をやるのか」「何のためなのか」ということを一人ひとりが腹落ちしてることが一番大事で、一人ひとり腹落ちの手法は違うので、それをどうやって森林さんが、多様な考え方・価値観の選手を育てたか、ということはとても大きなことですよね。