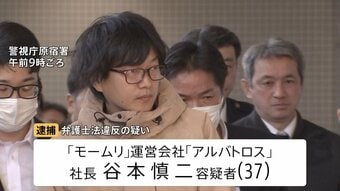予想外に低い数字でした。12日に発表されたアメリカの6月の消費者物価指数は、前の年の同じ月に比べて3.0%の上昇と、5月の4.0%から大きく鈍化しました。
FRBが重視するエネルギーと食品を除くコア指数も4.8%の上昇と、こちらも5月の5.3%から鈍化しました。サービス部門では依然高いインフレが続いているものの、アメリカのインフレはかなり鎮静化してきたと言っていいでしょう。
日本の消費者物価は、最新が5月分で、総合指数は前年同月比で3.2%の上昇でした。単純に最新の数字を比較すれば、日米のインフレ率は逆転した形です。
一転、円高方向に反転
予想外の「インフレ鎮静化」の効果は、すぐに市場に表れました。「FRBの利上げがあと1回に留まるのではないか」といった見方が台頭し、あらゆる年限で市場金利は低下、株価は上昇し、ドルは下落しました。円ドル相場も、1ドル=138円台まで円高が進みました。
その後も、アメリカの卸売物価が予想を下回ったことから、14日時点で1ドル=137円台に入っています。
円は、6月末には一時145円台まで下げていました。145円と言えば、2022年、日本政府・日銀が円買いドル売りの市場介入に踏み切ったレベルです。
市場では、再度の介入に警戒感が広がっていたほどで、わずか半月で風景は大きく変わりました。
円安を反転させた内田副総裁発言
145円まで進んだ円安を反転させたのは、アメリカの消費者物価発表より先に明らかになった日銀の内田副総裁のインタビュー記事でした。
日銀事務方出身の内田副総裁は、前の黒田執行部を支えて来た経歴もあり、緩和継続派と見られています。その内田副総裁が、7日までに共同通信と日本経済新聞のインタビューに相次いで応じました。
注目されたのは、YCC=イールド・カーブ・コントロールと呼ばれる長短金利操作の修正について、「金融仲介や市場機能に配慮しつつ、いかにうまく金融緩和を継続するかという観点から、バランスをとって判断していきたい」と述べた点です。
当たり前のことを言っているように見えますが、27日からの政策決定会合での政策修正が取り沙汰されている、この時期に、「今、修正の必要があるとは考えていない」とは言わずに、わざわざ「バランスをとって判断する」と述べたことは、政策修正に含みを残す発言と受け取られました。
共同通信にも日経新聞にも、一言一句、同じ答え方でした。メッセージを送る意図が明確にあったと、私は受け止めました。
2022年12月の黒田総裁時代に、日銀が突然、長期金利の変動幅を0.5%に拡大するという修正を行って、世間を驚かせました。
その際の日銀の理屈こそが、「金融緩和を継続するために、市場機能の歪みを生んでいる長期金利の変動幅の拡大を行う」という論理でした。
内田副総裁の発言は、金融緩和の継続のためであれば、市場機能に配慮して、例えば「変動幅を1%に拡大する」などの判断があり得ると言ってるようにも、受け取れます。