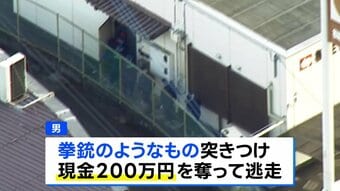種々の対策でようやく沈静化へ
昭和45年(1970年)前後に施行された数々の施策は多岐にわたりました。
◎上記、交通警察官の増員以外にも…
◎ドライバーや歩行者に対する交通安全教育
◎歩道や歩道橋、ガードレールの設置などインフラの整備
◎クルマに対する罰則の強化
◎公安委員会『交通の教則』の策定
じつは初めて「酒気帯び運転」という言葉が出てきたのもこの時期です(それまでは「酒酔い運転(最高刑・懲役6か月)」しかありませんでした)。
こうしたことが官民あげて行われたのです。

その効果は劇的なものでした…。

第一次交通戦争はこうして終焉を迎えました。昭和51年(1976年)からは死者数は1万人を切るようになり、ようやく「交通戦争」の語がメディアを賑わすことはなくなりました。
しかし…。
じつは話はここでは終わらなかったのです。
(後編『「安全なクルマを作れ!」第二次交通戦争と呼ばれた頃』につづく)
(アーカイブマネジメント部 疋田智)