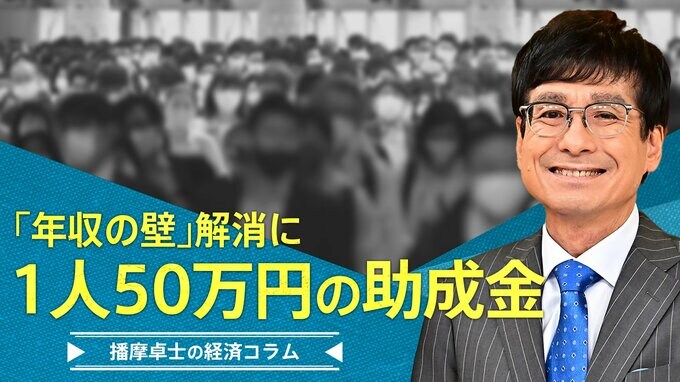とんでもない弥縫(びほう)策が飛び出してきました。106万円などの、いわゆる「年収の壁」を解消するため、政府が1人当たり50万円の助成金を支給する方針を固めました。しかも、財源は雇用保険料だというのです。制度抜本改革までの3年の時限措置とはというものの、「とりあえず」という岸田政権の、おきまりのパターンです。
「働き損」になってしまう「年収の壁」
「年収の壁」とは一定の収入を超えると年金など社会保険料の負担が生じ、逆に手取りが減ってしまうという問題です。
101人以上の企業で働く場合、月収8万8000円(年収にすると約106万円)を超える場合に社会保険料の負担が発生します。
壁を超えた瞬間に手取りが15万円もガクンと落ちてしまうというのです。
このため、働いている人は、時給が上がって「壁」を超えそうになると、労働時間をむしろ短縮する自衛策を講じるケースが続出し、現場では人手不足がさらに深刻化する事態となっています。
このほか「年収の壁」には、会社員の配偶者が社会保険の扶養対象から外れて保険料の支払いが生じる「130万円の壁」などもあります。
3年間の措置、1人最大50万円助成
壁を動かしたり、壁を坂に変えたりするには、年金など社会保険の抜本的な制度改革が必要になり、合意形成にそれなりの時間がかかります。
そこで、岸田政権は、3年程度の当面の措置として、一定の条件を満たした場合、最大で1人50万円の助成金を支給する方針です。早ければ今年度中に始め、そのために約200億円が必要と報じられています。
社会保険料は労使折半が基本ですから、労働者がいったん支払った保険料相当額が、企業経由で助成金として本人に支給されることになるのでしょう。その場合、助成金込みだと、働く人の手取りは減らず、いったん「壁」はなくなる形です。
不公平感満載の「とりあえず」助成
しかし、そもそも保険とは、保険料を「負担」した人が将来のリスクに際して「給付」を受けるものです。
今回のケースでは、新たに厚生年金に加入した人は、将来、厚生年金の給付を受けるわけです。一部の人についてだけ、実質的に保険料負担がないというのは、不公平な話です。
また、財源に雇用保険料をあてるというのも、解せません。雇用保険料は、本来、失業給付のためのものです。
すでに、育児休業給付や正社員化に向けた能力開発などにも使われていますが、「年収の壁」解消のための補填というのは、働く人たちの「リスク」に備えるという雇用保険の趣旨に、とても合致しているとは思えません。取りやすいところから流用するという発想が透けて見えます。