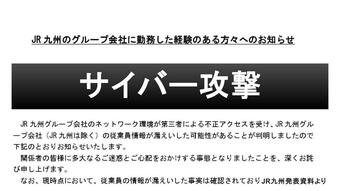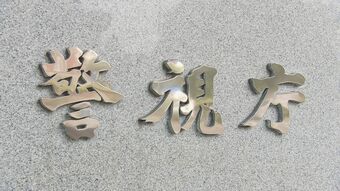再び円安が進んでいます。東京市場でも23日一時、1ドル=143円台まで円安・ドル高が進みました。アメリカの中央銀行にあたるFRBが年内あと2回の利上げを打ち出す一方で、日銀が依然として大規模緩和維持の姿勢を示しているためです。
金融引き締めが続くユーロに対しては、円安が一段と鮮明で、1ユーロ=156円台と15年ぶりのユーロ高・円安水準にまで下落しています。
消費者物価は高止まり
5月の全国の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が前年同月に比べて3.2%上昇しました。
日銀が重視する生鮮食品とエネルギーを除いたいわゆるコアコア指数は、4.3%もの上昇で、いずれも目標の2%をはるかに上回っています。エネルギー価格が22年比では落ちているものの、食料品などで価格転嫁の動きが続いているからです。
しかし、6月からは、補助金でいったん下がった電気代が大幅値上げされ、消費者物価の加速が予想されます。
足もとの一段の円安は、こうしたコストプッシュ型のインフレ圧力をさらに強めることになりそうです。
シナリオからの乖離に植田総裁も戸惑い
日銀はもともと原材料高や円安を起点とした今回の物価上昇はいったん弱まると見ていました。そこから需要に支えられた持続的な物価上昇につなげていくというシナリオを描いていたのです。
消費者物価上昇率が22年度は3.0%だったのに対し、23年度は1.8%と見通してるのは、そうした見立てからです。
持続的な2%上昇をめざす日銀としては、そうしたインフレ減衰をできるだけ小さなものに留めるために、足もとの物価上昇は、「のりしろ」を確保する意味で、多少高くても良いと考えていたはずです。
ところが、物価上昇は衰えるどころか、強いままです。植田総裁は、16日の記者会見で、「今は下がっていく局面だが、下がり方が思っていたよりもやや遅いかなという感触だ」と戸惑いを示しています。
その上で「企業の価格や賃金の設定行動に変化の兆しが見られ始めている」と持続的な上昇に手応えを感じていることも示唆しました。
要は、足もとの強い物価上昇が、持続的な2%上昇につながる可能性に期待しつつも、コストプッシュ型インフレが、需要が引っ張るデマンドプル型のインフレに、うまくバトンタッチできるかどうかに、なお自信が持てない心境を吐露した形です。