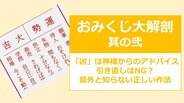坂部)行政が認めてくれるのは支えになりますか?
中村さん)そうですね。やはり行政が認めているとなったら、世の中が当事者を受け入れやすくなるのではないかなと思います。パートナーがちょっと怪我をしてしまったからその介護のお休みを取りたいと言った時に、会社に対して相手がパートナーであることを伝える時に、行政を認めてくれているのと、自分たちがそう言ってるだけというのだと、信ぴょう性が違ってくると思うんです。ただ…制度を利用することはカミングアウトの一種なので、カミングアウトをするのをためらうという人の場合、『パートナーシップ宣誓制度』は使いにくい部分はあると思います。
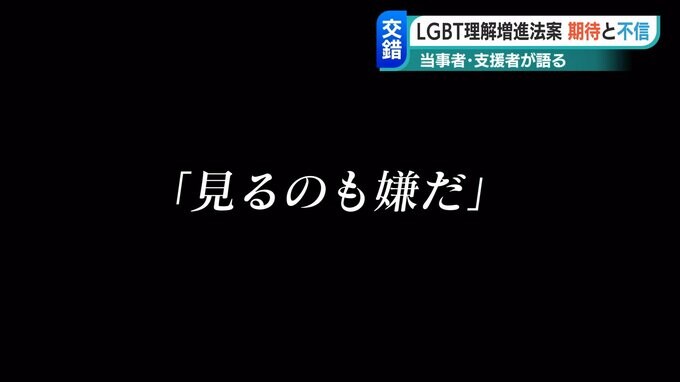
坂部)2023年2月、当時の総理大臣秘書官が「見るのも嫌だ」などと発言していました。「差別」と感じるような時はこれまでにありましたか?
中村さん)SNSで、あの“差別発言”について言及する人が増えました。その時に、割と交流のあったTwitterフォロワーが「LGBTQの人って権利ばかり求めてウザい」という趣旨の投稿をしていたのを見た時は、ダメージを受けました。その人は、私が当事者だと知らないですし、何気なく投稿しただけだとは思うのですが、こういう形で傷付くことは多々あります。カミングアウトをしていない当事者が受ける差別としてはこういったものが大きいと思います。
坂部)日本国内での「LGBT理解増進法」整備への機運が高まっています。法整備が進みつつある現状をどう思いますか?

中村さん)例えば日本には「障害のある人を不当に差別してはいけない」という法律があります。配慮してほしい部分がありますと言いたい時に、法律によって譲歩案を考えましょうとなるはずです。お互いの意見をちゃんと言い合って、「これは刑法に触れちゃうから駄目だよ」「それは他人の権利を著しく害するから認められない」とか…、そこでなるべくすり合わせができるのは、法律があるからこそだと思うんです。法律がないと、一方的に片方の意見を突き通そうとしたり、相手が折れたりしてしまう。それは、当事者側も、受け入れようとする側もそうです。お互いにすり合わせが難しい時があるんじゃないかなと思うので、法律をもとにした話し合いはあって欲しいよなと思います。