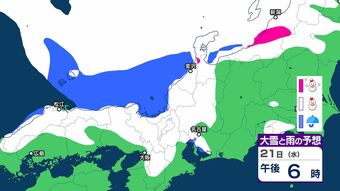制服は命にかかわる問題
永井先生は今回のジェンダーレス制服の導入で議論を主導してきましたが、そこには制服に関する様々な思いがありました。
船橋市立行田中学校 教務主任 永井恵先生
「私自身、トランスジェンダーであるという自覚を幼稚園の時から持っていたので、青春時代の象徴ともいえる学校の制服が苦痛や悩みの原因でしかなかったことが、何よりもつらかったという風に思っています。中学校の制服が家に届いた時、自殺を初めて考えました。私服の高校に進学後、仲間に寄付してもらった女子の制服を着て通った時期もありました。当時、体が男性の自分が女子の制服を着る事は、嘲笑や非難、病気や障害扱いの対象でしたが、自分としては自分らしくあることを実感でき、時間をかけてでも女性として生きていこうと決心するに十分だった経験です。制服についての悩みというのは、命に関わる問題でもあるという風に皆さんに捉えていただきたいと思っています」
永井先生は現在40歳。幼少期は、性的マイノリティやトランスジェンダーといった言葉が存在せず、自分が何者なのかわからない、説明のしようのないという暗闇の中でどう生きていけばいいのかずっと考えていたそうです。「自分自身のような経験をする生徒が二度と現れないように」という思いを胸に教員生活を送っています。
選択肢を増やす大切さ
行田中学校では、ズボンを履く女子生徒がいてもスカートを履く男子生徒は今のところ見られないと言いますが、このことについて、永井先生はこう話します。
船橋市立行田中学校 教務主任 永井恵先生
「実際に体が男性だと、体の変化を伴う思春期にスカート履くことは社会的にもハードルが高いのは間違いありません。ただし、たとえ選ぶ生徒がいなくても、学校として選べるというメッセージを発する意味を確認できたのはとてもよかったと思っています。選べるということは、選ぶ自分は何者かを問うことに繋がると思います。このことを大変だと思う生徒もいるかもしれないし、何も思わない生徒もいるかもしれません。それでも1人1人が多様性を織りなす当事者として、自分は関係ないという意識から脱却し、自分らしく生きるということにきちんと向き合っていってほしいと願っています」
永井先生は取材の終わりに「この動きが話題として取り上げられないような社会になって欲しい」と話しました。
“制服を自由に選べること”が当たり前になり、全国に浸透して欲しいと思います。
(TBSラジオ「人権TODAY」担当:宮内悠也)