「日々を回していくのが精一杯」他の『放課後児童クラブ』で働く人は
新潟市内の別の放課後児童クラブで働く女性に話を聞きました。

【市内の放課後児童クラブで働く女性】
「下校時間が重なってきた時は、かなり足の踏み場もないというような状態。なんとか日々を回していくのが精一杯。この状態だと『ああ今トイレの中で具合が悪くなっていたとしても分かんないな』とか…」
また別の市内の児童クラブで働く男性は、人数が多くトラブルも起きやすいと話します。

【市内の放課後児童クラブで働く男性】
「おやつを個々にまとめておいて前の方に置いておいて、じゃあ持って行ってくださいねと言うと、そこにまたズラーっと行列ができる。その中で、横から入ってくる子もいれば、それを注意する子どももいる。そこで毎日けんかになる」
専門家は、国のガイドラインの面積はあくまでも最低基準に過ぎず「それを満たすだけでは足りない」と指摘します。
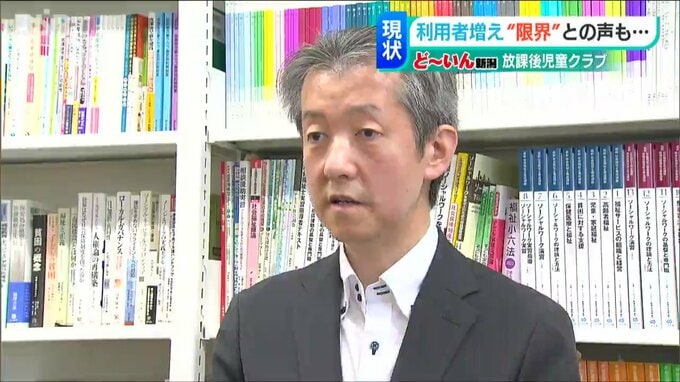
【新潟県立大学 植木信一教授】
「実質的にはこれは最低基準になっていて、この基準を満たせばいいとしている自治体が圧倒的に多い。そうすると圧倒的に狭い。それは果たして本当に子どもの健全育成に繋がるのかという疑問に繋がっていく」
新潟市が「待機児童ゼロ」を達成していることは評価しつつも、クラブが大規模化していることで弊害が生まれているとしていて、“質も意識するべき”だと話します。
【新潟県立大学 植木信一教授】
「待機児童対策の解消と、子どもたちの放課後の生活の場の“質”の確保。これを車の両輪として進めていく施策が、今後必要な方向性になるのではないか」

















