司法担当記者として寝屋川事件を取材
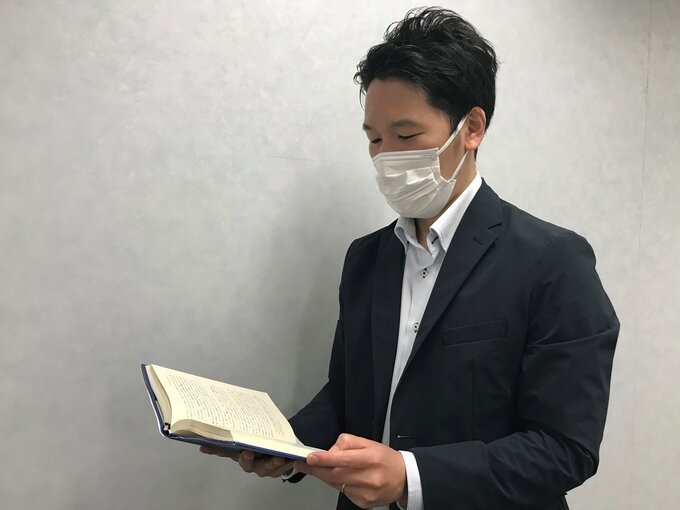
務めている。今回、全国2例目、近畿では初の特定少年実名発表の事件に接し、司法的な観点からの課題や疑問について考えながら、「実名」か「匿名」かの選択に向き合った。
今回の「特定少年」らと向き合った家庭裁判所や弁護士、また起訴と実名発表を決めた検察幹部らは、それぞれ実名報道をどう受け止めてきたのだろうか。
「原則逆送」と「不適切な養育の影響」の狭間にあるものは…

19歳の男は強盗殺人の罪で、18歳の男は強盗致死の罪で検察から家庭裁判所に送致され、少年審判を受けた。家裁は審判の結果、19歳の少年について「刃物で被害者を刺した際、被害者は抵抗のため体を動かしていた可能性があり、刃物が予想外に深く刺さった可能性が残る」などとして、殺意を認めるには慎重であるべきだと判断。検察側は強盗殺人罪で送致したが、家裁は強盗致死罪にとどまるとした。強盗致死罪は、原則として逆送する対象となっているものの、果たして逆送としてよいのか、裁判官の迷いともとれるものが決定文から垣間見えた。
【大阪家庭裁判所 真鍋秀永裁判官の出した19歳の少年に対する決定文(抜粋)】
「少年が事件と向き合い始め、内省を深めつつある」「少年が共犯者の提案に応じて強盗の計画に加わり、刃物を持参し用いるに至ったのは、少年が幼い頃から受けてきた不適切な養育が強く影響している」
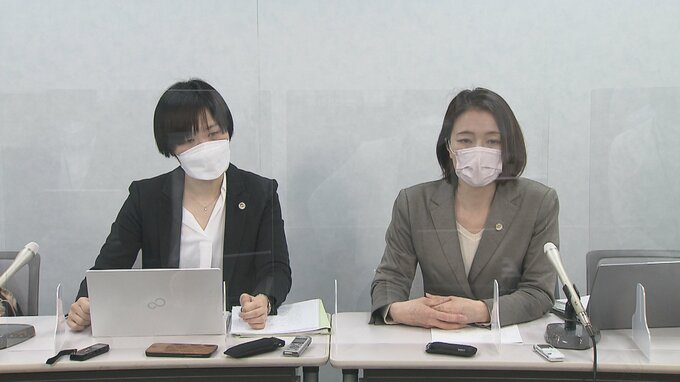
(19歳の男の代理人 玉野まりこ弁護士:写真右)
「本人が非行に至ったというのは、(親から)幼少期から受けてきた虐待の影響が多分にあり、家裁の調査の過程で明らかになっています」
(19歳の男の代理人 小西智子弁護士:写真左)
「“悪いことをすれば暴力を加えられて当然だ”という考え方に陥っていた」
また19歳の少年は事件後に被害者遺族に対し、「大切に育ててきた息子さんの命を奪ってしまったのは自分勝手な行動だ」などとする謝罪の手紙を送り、反省の気持ちを示したという。これらの点も踏まえて小西弁護士らは報道各社に実名報道を控えるよう求めた。
一方、家裁は、19歳の少年の逆送を決めた2日後、18歳の少年についても逆送を決めた。その理由について、「他の共犯者が刃物を持って犯行に臨むことは知っていたと認められ、被害者の対応次第では重大な結果が生じかねないと考えることはできた。それでも犯行に及び、自ら激しい暴行を執拗に加えたから、少年の責任を特に軽いとみることもできない」としている。同じ真鍋裁判官が担当したにもかかわらず、19歳の少年の決定文とは情状面での内容に違いがあるという印象を受けた。

















