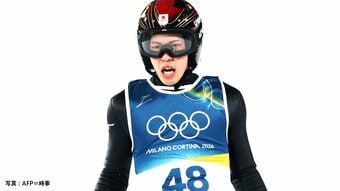「圧縮されてよかった」とホッ 経産省幹部は安堵
経済産業省は4月4日、大手電力7社(北海道、東北、東京、北陸、中国、四国、沖縄電力)の電気代について審査する専門会合を開催した。
議題は、“結果待ち”だった電気代の「値上げ幅」が結局どうなるかだ。規制料金は多くの家庭が契約しているため値上げは家計を直撃する。世の中の注目度も高い。
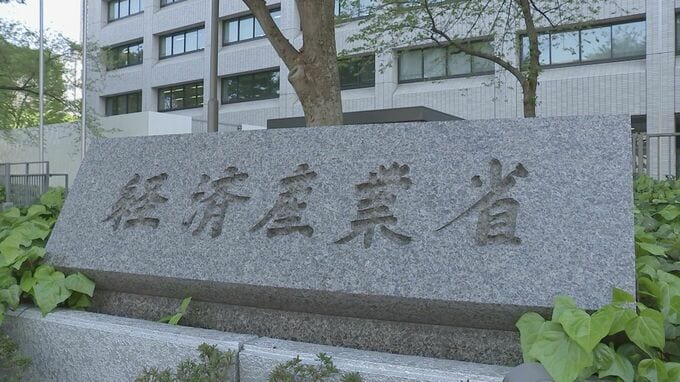
電気代の値上げは、電力会社が勝手には決められない。経産省に申請し、経産省が審査する決まりになっている。その審査には通常数か月を要する。
すでに大手電力7社は、去年11月から順次、国の認可が必要な規制料金の値上げを申請。ロシアのウクライナ侵攻による燃料価格の高騰や円安などで採算悪化したことが理由だ。今回、イレギュラーだったのは、審査中に“差し戻し”があったこと。計算の元となっていた燃料価格が申請後に下落し、円安が一服したため、国は3月に再算定を求めていた。
再算定の結果、4日までに7社のうち6社が値上げ幅を圧縮した。
値上げ申請中に、不祥事のオンパレード?
もう一つ異例だったのは、値上げ申請中に電力業界の不祥事が次々と明るみに出たことだ。
大手電力では社員らが、子会社の送配電会社などが持つ競合する新電力の顧客情報を不正に「カンニング」。一部は営業活動にも使っていた。また、「お互いのエリアの客には手を出さない」という「カルテル」も公正取引委員会から指摘。まさに不祥事のオンパレード状態だ。
しかも、2つの不祥事の共通点は、電気代を下げる電力自由化を骨抜きにする“反則技”だった点だ。いずれも自由競争を阻害するもので、電気料金の値上げにも繋がりかねないものだった。
不祥事続きの電力会社の値上げを、そのまま認めると、批判の矛先が経産省に向けられる恐れがある。規制料金の審査を担う経産省のある幹部は、国民感情も踏まえ「不祥事もあったなか、再計算で圧縮されてよかった」と安堵していた。