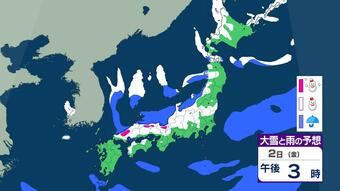■「国のありかたと自分が死んでいくこととの間に“矛盾”」

(安達卓也日記1944年1月9日より)
“果たして戦は是か?真の平和はかくも悲惨なる殺戮の彼方に求めらるべきか?”
(安達卓也日記1945年3月15日より)
“いかに特攻隊が続々と出現しても、中核をなす政府が空虚な存在となっては、亡国の運命は、晩かれ早かれ到来するであろう”

ノンフィクション作家 保阪正康さん
「国のありかたと自分が死んでいくこととの間には矛盾があるんだと。この国に満足して死んでいってるのではないという遺書をやっぱり書くんですね。国と自分を対置したときに、今自分が巡り合わせたことへの運の悪さ、悲しさ、しかしこれを越えていくんだということの矛盾と闘いながら」
一方的に戦争を始めた国家が、一方的に個を奪っていく不条理。そこに次の世代は何を見るべきなのか。
保阪正康さん
「個人の意識の集合体が国家の意識を作っていく。市民という基本的な人権を理解している人たちが市民社会を作っているような国家は基本的人権を尊重する国家になる。それがないと、国家は常に強圧的であり、国家の方向方針に対して国民は従いなさいと」
その先にあった特攻作戦。保阪さんは、美化するなど本質をすり替えるのではなく、なぜこれが起きたのか、彼らが生き続ける歴史の中で論じることが重要だと考えている。
保阪正康さん
「歴史的想像力ということですね。重要なことは歴史の一つ一つが自分とどう関わったのか、もし自分の時代だったらどうだったのか、ということを自分で問いを出し、答えを出していく」
“個の抹殺”を正義とした国家の過去の歴史が示していること。それは学徒出陣で特攻隊員になった体験を持つ、茶道裏千家前家元の千玄室さんにとって大切な価値観をより明確にした。
千玄室さん
「日本の国体を汚されないように汚されないように、こればかりした。日本の国を誇り高い国だと思わせる。ちっともそういうことはない。高揚ばかり考えて。精神的な高揚より大事なのは人間性ですよ」
(報道特集 4月30日放送)
※情報提供は番組ホームページまで