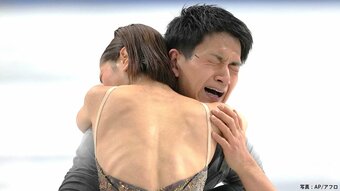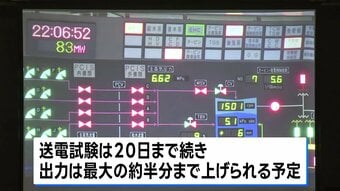報道特集で2021年11月6日に放送した「ネオニコ系農薬 人への影響は」への反響が続いています。番組で取り上げたのは、ミツバチが消えた原因ともいわれる農薬、ネオニコチノイド系の殺虫剤について。害虫だけでなく益虫、魚や鳥、そしてヒトにも影響を与える可能性があるとの懸念が浮上しています。EUなどで規制の動きが進む中、そのリスクをどう評価すればいいのか、専門家を取材しました。
■「一番不安なのはモロに薬液を浴びる俺たち現場の農業者だよ…」
今回のVTRはYouTubeにて、放送からちょうど一カ月で100万回を超えて視聴され続けています。そのコメント欄に、農業従事者と思われる方の声がありました。
「一番不安なのはモロに薬液を浴びる俺たち現場の農業者だよ…」
直接、ネオニコ系農薬を使う農業従事者はもちろんですが、実は、私たち一般の国民も食品を通してネオニコを微量ですが摂取しています。例えば、東京都は都内で販売しているコメや野菜など食品の残留農薬を毎年調査していて、令和2年度では、いずれも食品衛生法で定められた基準値を下回りますが、全体の約25%から検出され、その半数はネオニコでした。
ネオニコは農作物など植物への浸透性・残効性が高く、洗っても落ちにくいのが特徴です。こうして食べ物に残った農薬が人体に影響を与えるリスクについては、もちろんちゃんと調べる必要があり、国は農薬登録の際、様々な試験で毒性を検証して、規制値を決めていきます。
■“治験”はしない農薬

コロナ禍で広く知られるようになりましたが、医薬品メーカーが開発した「薬の候補」をヒトに使って、効果や安全性などを確認する臨床試験のことを「治験」といいます。ところが農薬の場合、農業従事者はもちろん少量ながら消費者への曝露も想定されますが、その候補をヒトに使っての治験は行われていません。
代わりに行われるのが、マウスやラットでの動物実験です。発がん性など様々な実験を通して、どのくらい農薬を使うと毒性が表れるのかを数値で示します。その数値をベースにヒトに当てはめて国の規制が決められていくのです。