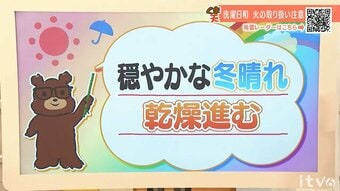◇「心身耗弱」か「心神喪失」か
裁判の冒頭陳述で検察側は、森松被告が犯行当時、統合失調症を患うなどの心身耗弱状態であったことや、判断能力などが低下していたと認めた上で「妄想がなければ犯行はなかったが、妄想が、放火や殺人を直接促すものではなかった」と指摘した。
そして「『自分が死んだら母の介助をする者がいなくなる、妹では世話ができない、ならば家族3人で死のう』という流れは、元々の性格など、正常な部分による判断」として、刑事責任に問えると主張する。
一方の弁護側は、心神喪失の可能性もあったとして無罪を主張した。
裁判の争点は、放火の故意性、母親への殺意、刑事責任能力の有無となった。
◇積極的な殺意認定「ためらわれる」
1月24日の判決公判。
高杉昌希裁判長は「火を付けたときに、家が燃える可能性までは意識していなかった」とする森松被告の供述を退け、ガスに引火した火が周囲に燃え移る認識はあったと、放火の故意性があったと結論付けた。
母親への殺意については「母親が死亡したと聞いたとき、自分の行為が原因で死亡したと分かったが、悲しんだだけで驚きはなかった」と指摘。
「殺さなければならないと考えていたとまで認めることはためらわれる」とした上で、認定した。

責任能力については、森松被告は当時、統合失調症のほかに境界域知的障害という精神障害があり、被害妄想のほかに、思考能力や判断能力の低下があったと指摘。
次々と自殺の方法を試した犯行当時の行動に触れ、「周囲の状況を認識して、自分の行為の意味を理解して、それを選択する能力が著しく低下していたが、完全には失われていなかった」ことから、心神耗弱状態にあったと判断した。
犯行について、住宅の密集地での放火は「極めて危険」なものと指摘。
寝たきり状態だった母親が逃げることができないまま焼死したことに触れ、「命が絶えるまでに感じた苦痛や恐怖は非常に大きかった」「愛情を注いで育ててきた息子の行為によって突然生涯を閉じることを余儀なくされた」と非難した。
◇献身的な介護「恨むに恨めないような心情」
一方で「母親は森松被告から献身的な介護を受けてきて、森松被告のことを恨むに恨めないような心情に至ることは容易に想像できる」とも述べ、森松被告が、寝たきり状態となった母親の介護をしてきたことや、統合失調症で長年精神状態が不安定だった妹と同居していた事情に触れた。

「境界域知的障害の影響もあってか、豊富な言葉は出てこないものの、母親について大変なことをしたという思いを述べていて、反省がうかがえる」「やけどを負って怖い思いをした妹も、早く帰って来て欲しいと思っている」ことなど「一定程度酌むことのできる事情」を挙げ、懲役6年の判決を言い渡した。