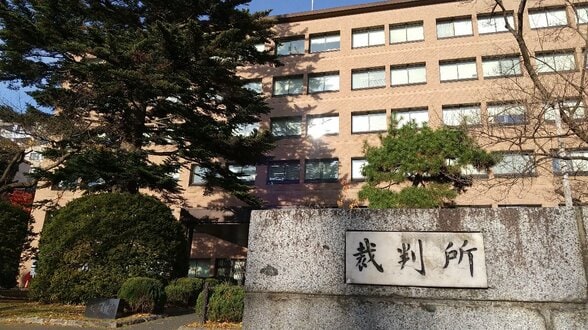「テレビ」と「インターネット」のこれからの関係は?
ーいま「テレビ離れ」が進んでいて、インターネットと真正面から向き合わなければいけない時期に来ています。YouTubeを運営する側から見た場合、「放送局」と「インターネット」との関係は、今後どんな形になり、どう高め合っていければと思いますか?

今後は「YouTubeを通して、そこでまずテレビ局のことを知る」というような流れもあると思います。ですので、ぜひ「視聴者の方と接する機会」をどんどん増やしていただいて、それでそこで知った情報をもとに、また「テレビの方を見たいな」という風な流れが出来れば...そういうことはすごく大事だと思います。

ですので、例えばYouTubeで事前に何か新しい取り組みをやってみて、そこでできたことが番組に形を変えてテレビの方に流れていくというような、その映像・番組作りの流れが変わっていくということも、可能性としてはあるのではないかなと思います。
YouTubeで変わる?地方の未来
ーあとは、「地方の情報」「地方の観光地」がエリア外に動画で紹介されることで、その地域に人が来るような「地域活性化を担う可能性」もありそうですね。
大いにあると思います。実際に「人が行動に移るまでに気持ちが高まる」というのは、それはまたそれなりのやり方をやっていく必要はあると思うので、一度で1本の動画で終わることではなく、何回もシリーズでその魅力を投げかけ続けて、本当に「行きたくなってくる」という気持ちを高めることができれば、やり方はあると思います。

【取材後記】
この記事で弊社の動画が気になったという方は「YouTube RSKイブニングニュース」で検索してチャンネル登録・高評価よろしくお願いします!という、耳馴染みのある決まり文句はさておき。。。
放送の未来は、テレビ局の未来はどうなるのか...それは2023年4月の時点では、率直に言うと全く分かりません。我が家の小学生たちも、テレビで “番組” を観るのは、TBSの朝の「THE TIME,」と「青い未来の世界のネコ型ロボット」「カスカベの幼稚園児」「黄色いスポンジ」のアニメくらいで、あとは完全に「YouTubeの受像機」と化しています。確実に若い世代がテレビを観なくなっていることを、足元から痛感しています。

ただその一方で、YouTubeをはじめとしたネット上にも我々のニュースは進出し、エリアを飛び越えて全国各地さらには世界中で見てもらえるようになった、さらにはテレビの受像機ではない、どこでも持ち歩くスマホの中にも入り込めるようになった...何とも複雑なもので、本当に「時代の移り変わり」を感じています。

デジタル化によって中央と地方が「ボーダーレス」になりつつある空気を、いま私たちは「ネットニュース」を通じて特に感じています。そんな中、いま出来ることは「愚直に地元のニュースを放送を通じてエリアの人たちに、かつネットニュースを通じて全国の人たちに伝え続ける」こと。そしてそのニュースがいつか誰かの喜びになり、時には誰かの救いにもなれれば、また社会が良い方向に向かうきっかけ作りができればとも考えています。その本分を忘れることなく、「メディアの未来」を地方から引き続き模索していきたいと思います。(RSKイブニングニュース編集長 武田博志)