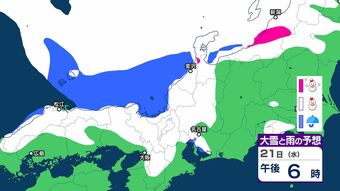まだAIはクリエイターの「想像を超えてこない」
野村:人間が書くのが主だとしても、その制作プロセスにAIをサポートとして導入することはあるのでしょうか?
岩井:それはあり得ると思っていて、私はAIが「ワープロ」のようになっていくと考えています。
90年代にワープロが普及した時、多くの先輩作家から「手で書いていない小説は良くない」という意見が出たそうです。ペンで一字一字書くからこそ何かが備わる、と。でも今や、ほとんどの作家がパソコンで書いていますよね。おそらくAIもこうなる気がしています。
AIに本文を書いてもらうことは難しいかもしれませんが、私たちの執筆を強力にサポートしてもらうことはできるでしょう。例えば、誤字脱字の発見能力は、もう人手でやるのが馬鹿らしくなるくらい高いです。他にも、プロットの穴を探してもらったり、物理トリックの矛盾をチェックしてもらったり、そういう壁打ち相手としての役割は十分にあると思います。
野村:私も番組企画の案出しで壁打ち相手として使うことがありますが、まだ自分の期待を超えてこないな、と感じることが多いです。
岩井: そうなんですよ。今のAIは、過去のものを学習して「それっぽいもの」を出すのは得意ですが、発想を飛ばすことはまだ難しい。全く違う分野のものを無理やりくっつけた時に起きる奇跡のようなものは、まだ生み出せない印象です。
野村:この話はまだ答えが出ていませんが、今がまさに分岐点なのでしょうね。今後は、人間がやる意味があるコンテンツと、そうでもないコンテンツに分かれていくのだろうなと強く感じます。
岩井: 「コンテンツ」という言葉が少し大雑把すぎるのかもしれません。「文字で書かれたもの」と一括りにせず、「文章」と「文書」のように細かく分けていくと、すごく見通しが良くなると思います。
野村:たとえば本の装丁などは、最後まで人間がやる方になりそうな気がします。
岩井: 装丁は人間だと思います。装丁家の方が私の作品を読んで、内面で消化して出てきたものを、対話しながら選んでいく。このプロセスに価値があるんです。
一人の人間の考えだけで決まっていくのが良くないからこそ、編集者や装丁家という仕事がある。そう考えると、AIはどこまでいっても今の段階では「道具」に過ぎないのかなと思います。
これがまた、「AIだよ」と明かされても誰もがっかりしないような世の中になってきたら、その時は私も、また会社勤めを始めるかもしれませんね。
<聞き手・野村高文>
Podcastプロデューサー・編集者。PHP研究所、ボストン・コンサルティング・グループ、NewsPicksを経て独立し、現在はPodcast Studio Chronicle代表。毎週月曜日の朝6時に配信しているTBS Podcast「東京ビジネスハブ」のパーソナリティを務める。