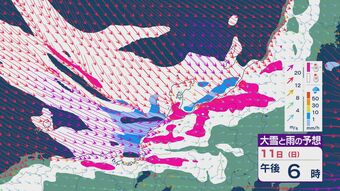日本人の気質に合わない「役不足」本来の意味
「役不足」の意味変化は今後どうなるだろうか。本来の意味「本人の力量に対して役目が軽すぎること」で使うと、謙虚な態度を好む日本人には「偉そうな人」と思われかねない。異なる新しい意味「本人の力量に対して役目が重すぎること」の方が日本人の気質に合っていることを考えると、むしろ異なる意味の使用率が今後高まる可能性がありそうだ。たとえ本来の意味での理解が増えたとしても、日本人気質に合わないという理由で「役不足」という言葉自体が使われなくなっていくように思われる。
他にも、時代の変化に伴って本来の意味での理解が難しくなってきた言葉には、「情けは人の為ならず」(「ならず」の「なら」が古語の断定助動詞「なり」であるとの理解が困難)、「馬子にも衣装」(「馬子」という言葉が理解されなくなった)、「かわいい子には旅をさせよ」(危険な「旅」から楽しい「旅」へのイメージの変化)、「濡れ手で粟」(穀物の「粟」を知る人が減り「泡」と誤解)などがある。
言葉の意味は時代とともに変化するものだが、SNSの普及によって、その変化の速度や影響範囲が拡大していることが今回の調査からも読み取れる。言葉の本来の意味を知ることの重要性だけを論じるのではなく、その変化に相応の理由があるとすれば、時にその変化を受け入れる柔軟さも必要だろう。
加藤和夫
福井県生まれ。言語学者。金沢大学名誉教授。北陸の方言について長年研究。MROラジオ あさダッシュ!内コーナー「ねたのたね」で、方言や日本語に関する様々な話題を発信している。
※MROラジオ「あさダッシュ!」コーナー「ねたのたね」より再構成