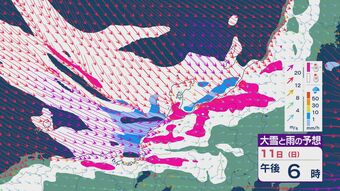言葉の意味変化 「役不足」の興味深い動向
調査では「付かぬこと」「したり顔」「にやける」「役不足」「潮時」の五つの言葉について、本来の意味と異なる新しい意味のどちらで理解されているかがも調査された。
「付かぬ事」は、本来の意味「それまでの話と関係のないこと」の回答率が45.6%、異なる意味「些細でつまらないこと」が41.6%と、わずかに本来の意味が優勢だった。ただし30代以下では異なる意味の回答率が5割を超え、16-19歳では57.9%に達しており、今後は新しい意味の使用が増えていくと予想される。
「したり顔」については、本来の意味「得意げな様子」が64.5%と、異なる意味「知ったかぶりしている様子」の25.1%を大きく上回っている。
特に注目すべきは「役不足」の意味変化である。本来の意味「本人の力量に対して役目が軽すぎること」が45.1%、異なる意味「本人の力量に対して役目が重すぎること」が48.9%と、異なる意味の回答率がわずかに上回った。
しかし、過去の調査と比較すると、2002年度に27.6%だった本来の意味の回答率が、その後の調査では40.3%、41.6%、45.1%と徐々に増加していて、これは他の言葉の意味変化(異なる新しい意味が次第に増加する)とは逆の傾向を示す点が興味深い。
「役不足」の本来の意味が理解されなくなってきたことへの、世間の批判的論調や学校教育の影響が考えられる。年齢別で16-19歳が本来の意味での理解率が最も高い(55.1%)ことは、学校教育の影響を思わせる。