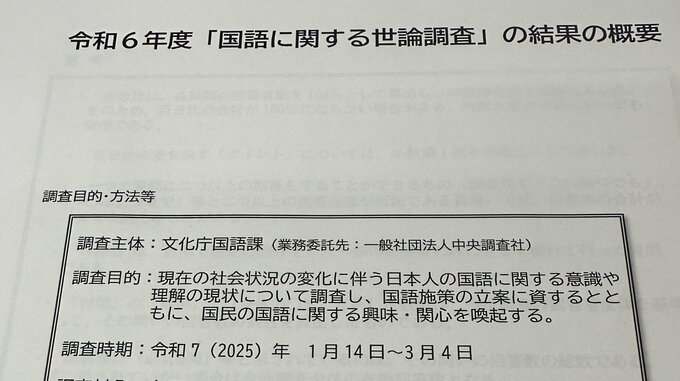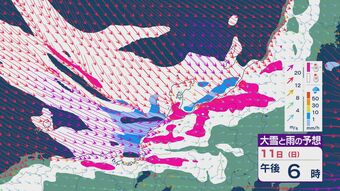文化庁が令和6(2024)年度に実施した「国語に関する世論調査」の結果が9月26日に公表された。この調査は前年度末の1月14日から3月4日にかけて、全国の16歳以上の6000人を対象に行われ、3498人(58.3%)から有効回答を得たものである。MROラジオあさダッシュ!「ねたのたね」コーナーでおなじみの言語学者・加藤和夫金沢大学名誉教授が今回の結果から、SNSの影響や言葉の意味変化について注目すべき点を紹介する。
初めて調査されたSNSの影響と課題
今年の調査では初めてSNSの使用、影響、課題に関する項目が設けられた。SNSのメッセージのやり取りで戸惑うことについて、最も多かった回答は「やり取りが面倒に感じることがある」(50.8%)で、次いで「相手の考えや感情が分かりにくい」(45%)、「情報が本当かどうかを判断しにくい」(43.5%)と続いた。これらの回答は年齢を問わず上位に挙がっており、SNS利用における本質的な課題を示している。
また、SNSの普及による言葉への影響については、全体の約9割が「影響がある」(「大きな影響があると思う」と「多少影響があると思う」の合計)と回答した。年齢別でも70歳以上の80%を除き、どの世代も9割を超える高い割合となっている。
具体的な影響としては、「略語が増える」(80.1%)と「言葉の新しい使い方や新しい言葉が増える」(76.9%)が特に多く回答された。これらはSNSの世界に限らず、若者言葉の特徴とも重なる点である。さらに「短い言葉でのやり取りが増える」(73.1%)、「十分に吟味されないまま使われる言葉が増える」(67.2%)、「世代間の言葉の使い方の違いが大きくなる」(64.4%)なども6割を超える回答率だった。