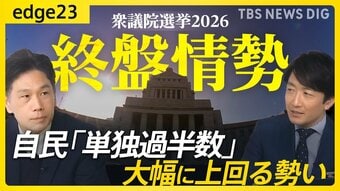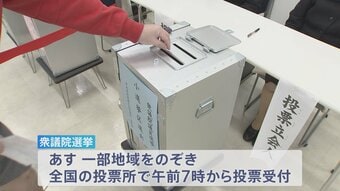■なぜ義務化しないのか、どこまで普及するのか
向井治紀・デジタル庁参与
「現実的な落としどころはかなり政権、あるいは官邸なり大臣がどういうふうに考えられるかというのもあろうかと思いますが、考え方としては免許証、それからコロナのワクチン、コロナのワクチン接種率(2回接種は8割)ぐらいはいくんじゃないかなと個人的には思っています。来年の3月とかっていう区切った時間ではなくて、近い将来という意味です」
「一方で100%という話になるとそれはすごく難しい。というのは、マイナンバー通知カードというのがあるじゃないですか。あの通知カードが、実は本人に100%届いてない。マイナンバーというのは住民基本台帳制度をもとに作られているんですが、住民基本台帳制度に書いてある住所にいない人がいて、当初は5%ぐらい届かなかった。その後、自治体がものすごく努力をして努力をして、それでも1~2%くらいが届いていない。だからそこまでは絶対行かないわけです」
マイナンバーカードの普及が進む今、「マイナ保険証に一体化されることで、カードの取得は実質義務化されるのに、法律では義務とは書かれていない」「国民皆保険のはずなのに、カードを持っていないと健康保険のサービスを受けられなくなるのでは」といった批判が多く寄せられている。
それならばいっそ、カード取得を義務づける考えはないのだろうか。
向井治紀・デジタル庁参与
「義務づけるという議論は昔からあって、国会の先生方の意見で、例えば罰則なしで義務づけるというのはないのかとかですね、そういうような議論はありましたが、本格的に議論をしたことは一度もないです。取得時に本人確認するので、出頭しないといけないとか本人の行為を伴うものを罰則付きで義務化するのは相当難しいと思います」
そのうえで、カードを持たない・持ちたくない人に対しては、従来通りのサービスを提供する代わりに、より割高の対価を要求する、高速道路でのETC(電子料金収受システム)のような状況になるのではないかと語った。
向井治紀・デジタル庁参与
「マイナンバーカードがあることによって、公的・民間も含めて社会的なコストが下がる効果というのはすごく大きいわけです。カードを持ちたくない人は、その分の効果を、ある意味、少なくしている分だけの対価を払う必要が出てくるというのがETCの考え方で、それに近い考え方では十分あり得るのではないかなと。そういう方向に進む可能性は十分あると思いますね」
TBS政治部デスク 川西全