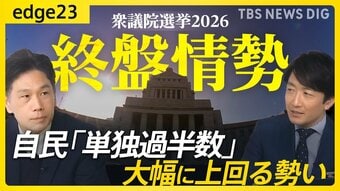■「ミスター・マイナンバー」が実現した無料化と”最大の後悔”

向井治紀・デジタル庁参与
「今はマイナンバーカードに遅れて、EUで『eID』というのを盛んにやるようになっていて、フランスなんかは半分ぐらいいっているんですかね。あとはみんな北欧の人口規模の小さい国、エストニアでも数百万ですし、スウェーデンとかでも2000万ぐらいのレベル。韓国は元々紙でチップのカードじゃなく、アメリカは全然ない」
実は、マイナンバー法自体には以下のように書いてある。
「第十八条の二 機構は、第十六条の二第一項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。」
つまり、手数料を取る可能性があったのだ。なぜ、最終的に無料となったのか。
向井治紀・デジタル庁参与
「これは、額は後で決めるという話だったんですけども、国会で答弁、当然質問出るわけですよね。法案は出したけど額が決まっていないわけですから『いくらやねん』と。マイナンバーカードが世間に出るのは、その法案が成立して1年後の話になるので、次の予算なんですね。その法案がかかっている国会の、次の予算の話なので額は決まってないんです」
「当然のことながら役人的答弁というのは『予算編成で決めます』という話だったんですが、これはもう単に自慢話じゃなくて事実を述べます。私は国会答弁で『無料が望ましい』とその時、答えました。こういうのは、しょうもない金をとっちゃ間違う。これはかなり大胆なことで、役所の、証明書でタダなものって実はないんですよ。例えば戸籍証明でも住民票でもみんなで200円、300円取るんですけども、これはもうタダにするというのが、将来こうなってほしいという、当時の、マイナンバーカードをやっていた人間の思いが入ってると思っていただいて良いんじゃないかと思います」
そんなマイナンバーカードをめぐって向井氏がひとつ、後悔していることがある。カードの“名前”だ。

向井治紀・デジタル庁参与
「個人番号カードでもマイナンバーカードでもない別の名称の方が良かったんじゃないか、本人認証カードとか…というのは今となってみれば痛恨の極み、私個人的にはすごく後悔しています。やはりマイナンバーを使ってるという誤解があまりにも多いのと、マイナンバーカードのチップを使うこととマイナンバーを使うことの混同があまりにも多いから、やはり名前は違った方がよかったなとは思います」
マイナンバーカードの普及率は申請ベースで7568万件、全人口の60.1%に達した(11月27日現在)。政府は運転免許証と並ぶ、約8100万件の申請を年内に達成することを目指している。また、2023年3月末までに「ほぼ全ての国民に行き渡らせることを目指す」としている。
ただ、向井氏は「全ての国民が持つのは無理」と明言したうえで、現実的な落としどころについて次のような数字を口にした。