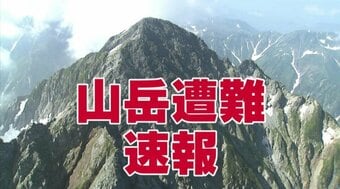■教員たちの実感
複数の現役教員に聞くと、やはり多くが、いじめの一般化や流動化を実感していた。
兵庫県小学校教員・30代:
いじめの一般化を強く感じます。それは子供たちの環境の変化にも関係していると思います。スマートフォンの普及、SNS・オンラインゲームの利用などで、あらゆる場面でいじめが起こりうる環境にあると感じています。
小学校教員・20代:
クラスでアンケートをとると「暴力や暴言や無視などでイヤな思いをしている」と数人は必ず被害を訴えてきます。それも、あんなに楽しそうなあの子が・・・という思いです。子どもの世界には大人のアンテナが行き届きづらいと実感しています。
東京都小学校教員・40代:
善悪の判断がつかず、“なんでやってはいけないのか”を説明しなくてはいけない場面も増えています。“ルールを守る”とか“他の人の嫌がることをしない”という意識が薄く、悪気がなく暴力を振るってしまう場面も見られます。
大阪府小学校教員・40代:
いじめの要因は、ストレスと排他性などと言われますが、様々な環境や情報のもと、毎日、ギリギリの生活をしている子どもたちが増え、余裕がなくなってきているのかもしれません。
静岡県小学校教員・20代:
女子のグループでは、誰か一人が無視される時期が終わると、別の子がターゲットになる事例を多く聞きます。
大阪府小学校教員・40代:
一人っ子が増え、核家族化が進み、多くの人と共同生活している子どもも減り、相手との距離感を掴むのが難しくなってきていると感じます。そもそも“いじり”と“いじめ”の境界線が難しく、“いじめ”を自覚していない子どもたちが多くいます。さっきまで仲良く遊んでいた子どもたちが、ちょっと目を離すとケンカしている。昨日まで、仲良く話していた子どもたちが、ちょっとしたきっかけで距離を置くようになる。立場があっと言う間に変わってしまうのは、現実として多くなってきているように感じています。
■いじめ対策の見直し

故・森田洋司(鳴門教育大特任教授、大阪樟蔭女子大元学長、大阪市立大名誉教授)
写真提供:鳴門教育大学
森田洋司は、こうした現状を踏まえ、これまでのいじめ対策で、見直さなければならない点も出てくると語った。
「いじめの一般化と流動化を、私は非常に深刻に受け止めています。これまでのいじめのとらえ方には、若干限界が出てくるからです」
例えば、児童生徒の理解について。1980年代から2000年代のはじめまで、いじめっ子の性格、パーソナリティ、特性などの分析があった。被害者の特性も、行動と人格をくっつけて解釈していた。特に1980年代は、いじめっ子やいじめられっ子が、どういう子どもなのか、その間の関係はどうなのかを考える研究が盛んだったという。彼らに独特のパーソナリティがあるのではないかという捉え方をしていたのだ。
森田洋司:
その考え方はもう見直さないといけません。一人の子どもの中に、加害と被害、その両方を持つ、共存していると捉える必要があります。だからこそ「あ、この子は加害者だ」と特定の子だけに目をつけて指導や支援をするのではなく、もっと広く多くの子を、いや全ての子を対象にしながらいじめ対策をやるべきなのです。これまでの「問題行動が出たら対策を打つ」という方法だけでは不十分で、もっと基礎的な「いじめの未然防止」が現代では必要です。つまり単に問題に対応する「治す生徒指導」ではなくて、「育てる生徒指導」をどう展開するのか。
このように、森田は「いじめ対策」といっても、いじめという行為だけに絞っての指導では物足りないと訴えた。教職員だけでなく全ての大人が、何を子どもたちに培うのかを深く掘り下げて対応する必要があると述べたのだ。いじめ対策の大きな方向性を「事後的対応」から「未然防止」へ変えていく必要があると提言した。
執筆者:TBSテレビ「news23」編集長 川上敬二郎