■コロナ禍のもとでのいじめ予防
「コロナ×こどもアンケート」の調査を担当した国立成育医療研究センターの半谷まゆみ研究員(小児科医)は、コロナによるいじめの発生について「これまで何か他のことでストレスを発散していた子どもたちがコロナ禍でできなくなり、いじめることでストレスを発散している。
一方、例えば持病のため頻繁に鼻をかむ子どもが“コロナいじめ”にあうのではと不安に駆られている。子どもには残酷な面もあるから“ソーシャル・ディスタンスだ!”と言って離れることもある。その上、学校では普段マスクを着けているので表情が見えにくい。先生と子ども、子ども同士、コミュニケーションが取りにくく誤解も生じやすい。
お互いの変化に気づきにくい点にも注意が必要で、その分、先生方はしっかり不安の声に耳を傾けてもらいたい。家庭では親も子どものイライラを注意しがちだが、子どもも理由があってイライラしていると理解して、やはり話を聞いてあげてほしい」と訴える。
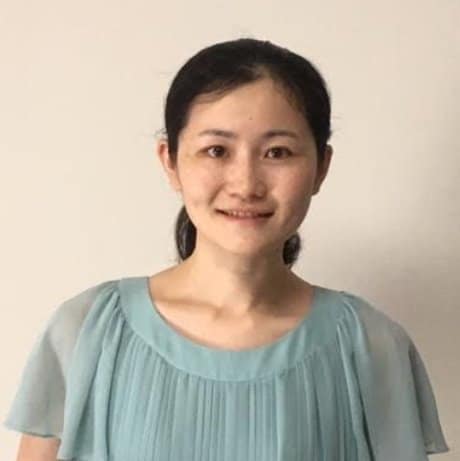
<次回は「いじめの流動化」>
こうして子どもたちの学校生活の中で「一般化(日常化)」が進むいじめは、コロナ等、そのときどきの世相も反映している。そして実はもう一つ、いじめの現状を表すキーワードがある。それが「流動化」だ。
【いじめ予防100のアイデア】第5回「加害者と被害者が入り乱れる“流動化”が進行中」
執筆者:TBSテレビ「news23」編集長 川上敬二郎














