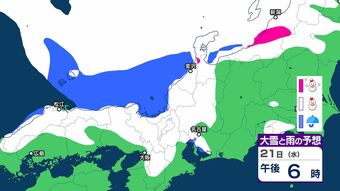足りない支援の受け皿「満室で断らざる得ないケースも」
困難を抱えた妊婦への支援は少しずつ拡充されてきているものの、その質と量にはまだ課題があります。田中さんは「居場所支援をおこなう団体が、満室によって半年で10人の支援を断らざるを得なかったという話を聞きました。ギリギリ満室になる前に入られた方と、その直後で断られてしまった方のこの違いを見るとすごく辛いものがあります」と語ります。
支援体制の地域格差も深刻です。あるリスナーからは「第1子と第2子を別々の自治体で出産した経験から、産後ケア事業などの支援体制に大きな差があった」という声が寄せられました。田中さんは「国は自治体に対して、妊産婦等生活援助事業の財源の半分を出すことになっていますが、残りの半分を出せる自治体と出せない自治体の差がどうしても残っている」と説明します。
また、地方では「うちの地域には望まない妊娠をするような女性はいない」と支援の必要性を否定する自治体もあるといいます。赤尾さんは「どの都道府県であっても、妊娠して孤立している、実家にいるけれども親には言えないなど、どんな状況であっても来たらいいよと言える、安心して過ごせる居場所があったらいい」と訴えます。
途切れない支援の実現に向けて
こうした状況を改善するために、赤尾さんは支援者のスキルと意識の向上が重要だと指摘します。「相談窓口を検索して相談に至っても、そこで支援が切れてしまうことが実際に起こっている」と懸念を示します。
理想的な支援の流れとして、赤尾さんは「よく相談してくれました」と受け入れ、途切れない支援の重要性を強調します
「この先、病院に行くお金がなかったとしても、誰にも言えなかったとしても、ここから出産後のことも一緒にやっていくから大丈夫だよと言える窓口がある。そして次につながった医療機関でも保健センターでも同様の対応がされることが重要です」
田中さんは「全国どこにいても同じ支援が受けられるところを目指していきたい」と展望を語ります。また、「自己責任」として片づけず、社会全体の理解を広げていくことの大切さも強調しました。
赤ちゃんの命と母親の人生を守るための支援。その入り口となる妊娠SOS相談窓口の存在を知ること、そして社会全体で支える体制を整えることが、今、求められています。
全国の相談窓口は「全国のにんしんSOS相談窓口」で検索するなど、一般社団法人全国妊娠SOSネットワークのホームページをご確認ください。