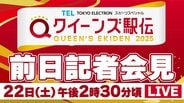過程を楽しむ強さも加わった山西
経験不足などが要因だった東京五輪の失敗も、集中力を欠いたブダペスト世界陸上の失敗も、その後の山西は克服してきた。厚底シューズへの対応はまだ完全ではなく、前述のように5~6月の3レースは「平均点が少し低い」という内容である。
それでも苦い思い出もある“東京”に臨む山西には、これまで以上の落ち着きが感じられる。冒頭で紹介した「2年間に色々なこと」が山西にあり、そのプロセスに充実感と自信を感じられているからだ。厚底シューズへの対応では、自身の経験と考察力、さらにはスタノと一緒に、イタリアで練習することで改善できる手応えがある。
「前足部にしっかり体重を残しつつ、逆脚を後ろから前に振っていく時間を取る必要があるので、そこを強調するようなトレーニングが重要だと思っています。それと他の選手が行っていることを見ることも大きなポイントです。去年行ったスタノとのイタリア合宿で学べたことが大きく、今年も7月にイタリアに行くことでまた新たな発見があるでしょう。そこで見えるものを大事にしたい」
レース展開的には「後半のバリエーション」が増えているという。「今までは速いペースで押し切って、相手を振り切っていく形でしたが、後半の削り合いになっても対応できます。レースの引き出しが増えてきていると思います」
オレゴン世界陸上も最後の削り合いだったが、厚底シューズに変更後では、今年の日本選手権は残り5~6kmでペースを上げて独歩に持ち込んだ。5~6月の3連戦2試合目のマドリードは、「出入りの激しい競り合い」(山西)になったが、パリ五輪銀メダルのC.ボンフィム(34、ブラジル)に5秒差で競り勝った。3試合目のラコルーニャは、15kmから山西がペースアップしてスタノらを振り切り、最後は川野将虎(26、旭化成)を4秒差で制した。
再び世界と戦えるレベルに戻って来られたのは、人との出会いが大きかったと実感している。
「紆余曲折を経て、様々な出会いがあり、支えをいただきながらの2年間でした。そうした経験を深みとして、新たな自分の表現として、東京世界陸上で形にできるのが1番いいですね」
来年2月に30歳となるベテランの力が発揮されそうだが、山西自身は「最初の世界陸上と似た気持ち」だという。この2年間が初めてに近い感覚の経験であり、18~19年の自身が強くなっていく手応えを感じていた頃に似た雰囲気もある。
山西が3個目の金メダルを取った時、19、22年と比べてどんな金メダルだったと言うか。そこも注目したい。
※写真はオレゴン大会(22年)で金メダルを獲得した山西選手
(TEXT by 寺田辰朗 /フリーライター)