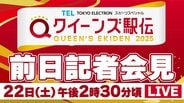東京五輪の敗因を克服してオレゴンの金メダルに
19~22年の山西には、どんなレースでも勝てるのでは、と思わせる強さと安定感があった。20~21年前半は新型コロナの感染拡大で国際大会出場機会こそなかったが、世界トップレベルの選手が多数参加する日本選手権に2年連続で圧勝した。19年世界陸上にも勝っていた山西は、21年東京五輪(札幌開催)では優勝候補筆頭に挙げられていた。
だが結果は銅メダル。中国選手が序盤で飛び出したが対応が後れ、中盤で追い上げることに力を使ってしまった。終盤でM.スタノ(33、イタリア)、池田向希(27、旭化成)と3人の争いになったが、17kmからスパートした際に警告と注意を立て続けに出された。山西を指導する内田隆幸コーチは、「今まで見たことがない顔のしかめ方でした」と当時話している。18km過ぎで2人から後れ、銅メダルは獲得したが、レース内容的には明らかな敗戦だった。
今の山西なら、違う戦い方ができたのだろうか。
「(コロナ禍で)直近のレースをする機会の不足や、あのときのような立ち回りをしてしまう経験値の少なさが響いてしまったと思っています。簡単に言うと経験不足、想定の甘さをすごく感じました。誰かがポンと飛び出した時の対処方法も、ですね。他の選手の揺さぶりに対応する方法と、自分が主導権を握って相手を振り回す方法、その2つがあれば東京五輪も良い方向に向かったかもしれません。あの時点ではできることをやったと思っているので後悔はありませんが、それらを経て先に進むにはどうしたらいいかを考えた結果がオレゴンの金メダルでした。そこはさらにブラッシュアップできているので、東京世界陸上に向かう今はあまり気にしていません」
オレゴン翌年のブダペスト世界陸上(23年)は24位。山西の競技歴で唯一、大きく“外した”国際試合である。厚底シューズの普及もあったが、それよりも山西自身がメンタル面で、集中し切れていないところがあった。
ブダペスト後に厚底シューズへの対応に取り組み始めたことで、技術は崩れたが、気持ちの面は立て直せたのかもしれない。山西自身もブダペストの失敗を、大きな問題点として言及することはあまりない。23年の失敗は繰り返さない自信があるからだろう。