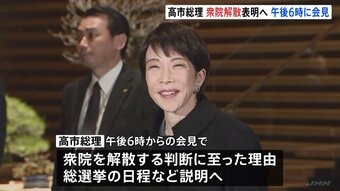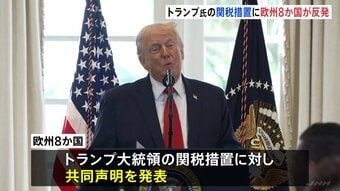フィッシングなどの手口によるインターネットバンキングでの不正送金の被害額が、上半期としては過去最悪のおよそ42億2400万円にのぼったことが、警察庁のまとめでわかりました。
警察庁によりますと、ことし1月から6月までのインターネットバンキングでの不正送金の被害額はおよそ42億2400万円にのぼり、上半期としては過去最悪となりました。
また、実在する企業を装ったメールで偽サイトに誘導しパスワードなどの情報を盗む「フィッシング」の上半期の報告件数は、前の年の同じ時期と比べおよそ56万件増えて過去最多の119万6314件にのぼりました。
去年の秋以降は、インターネットバンキングの更新手続きなどをかたった電話で情報を聞き出す「ボイスフィッシング」という手口も確認されています。
フィッシングの脅威は証券口座にも広がっています。証券会社を装うフィッシングメールの報告件数は、1月の104件から5月には7万3857件に増加。
それに伴い、証券口座の不正取引額も1月のおよそ2億8000万円から4月にはおよそ2924億円に急増していて、警察庁は関連が強いとみています。
また、企業を狙ったサイバー攻撃も深刻化しています。
データを暗号化して身代金を要求するコンピューターウイルス「ランサムウェア」による被害の報告は116件で、2022年下半期と並んで過去最多となりました。
中小企業の被害が過去最多の77%を占め、対策が比較的手薄なため狙われたとみられています。
ランサムウェア被害からの復旧費用について、1000万円以上かかった企業は全体の59%にのぼりました。
感染経路のおよそ8割はVPNなどのネットワーク機器からの侵入で、原因としてはIDやパスワードが簡単なものであったり、不要なアカウントが放置されていたりするなどの管理の不備が挙げられています。
実際に、管理が行き届いていない海外支社の機器から侵入され、国内の本社が被害に遭うケースなども確認されているということです。
警察庁は、基本的なセキュリティ対策の徹底と、不審なメールや電話には決して応じないよう、改めて注意を呼びかけています。
注目の記事
“空き缶拾い”で生きる男性に密着 無断での持ち去りは50万円以下の罰金へ…名古屋市の「禁止」条例がことし4月に施行

立憲・公明が「新党結成」の衝撃 公明票の行方に自民閣僚経験者「気が気じゃない」【Nスタ解説】

「カツ丼」「貼るカイロ」の優しさが裏目に?共通テスト、親がやりがちな3つのNG行動「受験生は言われなくても頑張っています」

受験生狙う痴漢を防げ 各地でキャンペーン SNSに悪質な書き込みも 「痴漢撲滅」訴えるラッピングトレイン 防犯アプリ「デジポリス」 “缶バッジ”で抑止も

宿題ノートを目の前で破り捨てられ「何かがプツンと切れた」 日常的な暴力、暴言…父親の虐待から逃げた少年が外資系のホテリエになるまで 似た境遇の子に伝えたい「声を上げて」

「timelesz」を推すため沖縄から東京ドームへ――40代、初の推し活遠征で知った “熱狂” 参戦の味、そして “お財布事情”