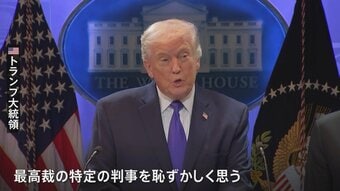■焦る総理「ワクチンが進まなければオミクロン株は抑えられないぞ!」
新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の猛威が続いている。2月3日、ついに全国の新規陽性者は10万人を超えた。しかし、3回目のワクチン接種率は4日公表分だと全体で4.8%。OECD加盟38か国の中で最低となっている。
「ワクチンが進まなければオミクロン株は抑えられないぞ!」
岸田総理は周辺に、ワクチン接種の遅れに焦りを見せているという。 政府内からはよく、この3回目接種の遅れについて「モデルナを打ちたがらない人が多いからだ」との声を聞く。確かにそれも実態だが、そもそも接種が遅れた一番の要因は、2回目からの接種間隔を前倒しするという判断が遅れたことにある。
■「8か月間隔」にこだわった厚労省、遅れた政府の判断
オミクロン株の出現により、「早くワクチンを打った方が良い」との声が高まったのは、今から遡ること3か月前、去年の11月だ。
“8か月間隔”に拘ったのは厚生労働省だった。3回目接種をめぐっては、厚労省が2021年11月11日、「2回目から6か月経過後から接種可能」とする薬事承認を行った。そして、11月15日、厚労省のワクチン分科会が「地域の実情に応じて6か月後に前倒しできる」とする方針を了承。しかし、政府や厚労省は、その後も“8か月間隔”を堅持し続けた。政府のワクチン接種を担当する幹部は今、このように語る。
「“8か月”に医学的根拠はなかった。日本としては、当時の欧米が8か月を基準にしていたことや市町村での混乱回避を理由に挙げるしかなかった。しかし、欧米諸国は、その後の方針転換が日本よりもずっと早かった。日本は、官邸と厚労省の調整が難航し、判断がズルズルと遅くなっていった」
欧米諸国などが次々と「3~6か月」への前倒しへ舵を切る一方、日本政府は方針変更に尻込みをした。当時、会見でも、後藤厚労大臣が「自由に地域の判断で前倒しを認めるものではない」と“原則8か月”を繰り返したほか、堀内ワクチン担当大臣も「6か月は例外であり、前倒しを検討する場合には厚労省に個別に相談を」と強調。医学的な理由かどうか聞かれた際にも、「接種体制を組むのが大変になってくる」と話すのが精一杯だった・・・。
■厚労省の“安全ライン”に配慮する官邸
一方、オミクロン株の感染者が国内でも少しずつ増え始めていた。11月半ば以降、専門家や全国の自治体から前倒しを求める声が続出した。11月21日には、全国知事会が政府に対し、前倒しの基準を明確にするよう提言。さらに、同月29日、小池都知事が官邸を訪れ岸田総理と面会した際、「7か月で抗体がかなり減少してくる」と言及している。この日は、政府がオミクロン株への水際対策を強化し、全世界からの原則入国停止を表明した日だ。
こうして、オミクロン株に対する政府の危機感が急激に高まってきた中で、ようやく前倒しの検討が始まった。一度目の前倒しを政府が発表したのは、12月17日。厚労省のワクチン分科会が「前倒しできる」と方針を示してから、実に1か月も経過していた。その内容は、一般の人は対象とせず、医療従事者や高齢者施設入所者らを「6か月間隔」に、一般の高齢者を「7か月間隔」に短縮するものだった。
この時もまた、厚労省のいわば“安全ライン”に官邸側が配慮する形となったのだ。