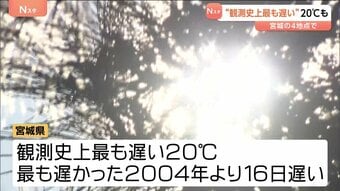■“立つ鳥跡を濁さず”文化の日本 退職代行サービスの意義とは…?
ーー退職代行サービスの経済的・社会的意義を教えてください。
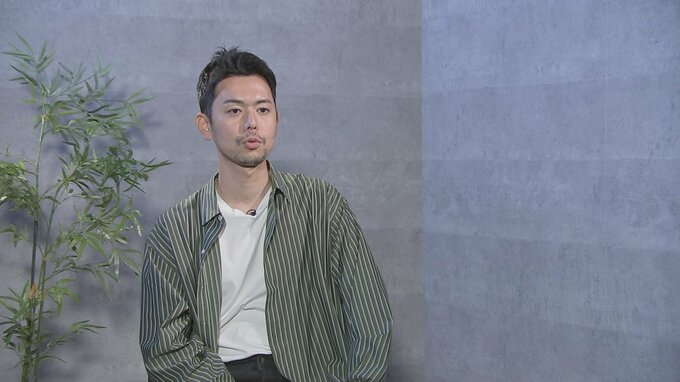
まずは、人材の流動化です。これはずっと日本の課題だと思うんですよ。斜陽産業から成長産業に人が動けばいいんだけれども、なかなか動かないのが現状としてあるので、そこは退職代行という事業が力になれる部分なのかなと思っています。なぜ人材が動かないかって、やっぱり辞めづらいからですよ。辞めさえすれば、人材は動くので、まず辞めやすい社会にするということで、人材の流動化を進めていくという点では一つ貢献できるのかなと。
もう一点が、労働者目線で見たときにメンタルケアとしては 非常に役立っているのではないかなと思っています。社会のセーフティーネットというか、今弊社に電話してくるお客様の中でも本当に呼吸ができないぐらい辛くて、もう出勤すること自体ができないという方もいます。極端な話、そういう方はそのような状況が続くと自殺してしまうんですよ。我々に頼むことで、その日から会社に行かなくてもよくなるので、自殺者を減らすという部分でも貢献できているのかなと思います。
一方で、企業側から見たときのことをお話しすると、退職するときは、みんな本音を言わないんですよね。「本当は上司の●●さんが嫌いだから辞めた」というのが一番の理由だとしても、絶対言わないんですよ。日本の”立つ鳥跡を濁さず”の文化ですかね。大体「家業を継ぐ」といった嘘をついて辞めるんですけど、うちには本当の理由を言ってくれるので、退職する本人の許可を取った上で、その本当の理由を企業に伝えることがあります。そうすると、「●●課長ってこんなにやばかったんですね」 のような、人事の人が今までわかってなかった、なぜ離職者が多いのかという本当の理由に会社側が気がつくこともあるんですよね。
■「時代について行けてない会社に、気がつく若者が増えた」
ーー日本の人材流動性は低いとのデータがある一方で、私の友人・知人には転職を経験している人が増えている印象があります。私個人の感覚では、若い世代の転職は増えているのではないかと思うのですが、新野さんはいかがですか。
そもそも転職サービスっていうものが例えば10年前と比べたら充実していますよね。SNSで気軽に転職できる時代にもなってきているので。それこそTwitterで就職活動するとか、若者だと当たり前になっていますよね。
転職のハードルも下がっているし、日本社会の先行きを考えたときに、このままこの会社にいたらまずいだろうと気づく若者が増えたのではないかと思います。いざ会社に入ってみないと、その会社がどう動いているのか、わからないじゃないですか。例えばこのコロナ禍で、そもそもリモートワークNGだと言っている会社もあって、「マジかよ」となるわけですね。時代について行けてない会社に、気がつく若者が増えたのかなと思います。