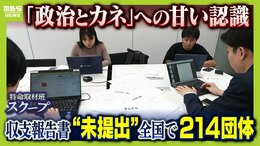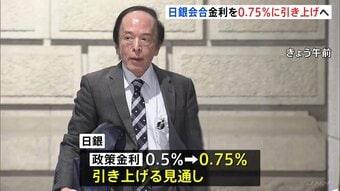問題の根底にある「アドネットワーク」という仕組み
こうしたことが起こる原因の一つにインターネット広告で主流となった、アドネットワークがある。
これまでの新聞・雑誌など紙媒体の広告は、広告主と広告代理店、媒体社の間でやりとりして出稿を決めていた。広告主はどの媒体のどの面に広告が掲載されるかを把握できた。だが、何百万ものメディアに広告を出稿するインターネット広告ではそんな丁寧なやり取りは無理だ。
そこで登場したのが、アドネットワークだった。広告代理店とメディアの間に入り、広告主の要望に合うメディアをプログラミングによって瞬時に選んで広告出稿を処理する仕組みだ。商品に適した読者を選んで出稿するので広告主が望んだターゲットに広告が届き、コストパフォーマンスもいい。
ただ、このターゲティングは過去の履歴などを元に行うので100%ではない。妻へのプレゼントを検索した後に女性向けの商品の広告がやたら表示されることがあり辟易するが、こうした「勘違い」が起こりがちだ。
広告表現の審査も莫大な数をプログラミングによって行うため、人の目に比べると緩い。刺激の強い広告の方が効果が出やすく、表示も多くなりがちだ。アドネットワークは、広告主の利便性のために「読者の気持ち」を犠牲にしていると言えるのではないか?
「情報健全性」が問われ出したSNS
また最近、ネットでは「情報健全性」が問われている。怪しい情報が多く真偽を確かめる必要があり、犯罪の場となることさえある。
顕著なのがSNSだ。Facebookでは昨年、詐欺広告がはびこり社会問題化した。著名人の画像を勝手に使って投資を呼びかけ、うっかりクリックするとやりとりが始まり、なぜかお金を求められて何百万円も損した事件が頻発した。さすがに最近はあまり見かけないが、見知らぬ者の怪しい投稿は今もよく見かける。知っている者同士がつながる安心のコミュニティだったのが、うかつに「いいね」も押せない怖い世界になった。
米国でトランプ政権になった途端、FacebookのCEOマーク・ザッカーバーグ氏はファクトチェックをやめると表明し、修正する気配はない。政権交替のたびにプラットフォームのトップが方針を変更するようでは、信頼できる場と言えるのか。
イーロン・マスク氏が買収したTwitterはXと名を変え、様々にルールを変更した。それにより、以前より荒れた場になってしまい、頻繁に投稿していた私も怖くて投稿を控えるようになった。平気で性的な画像が横行し、政治的に対立する勢力同士の荒々しいやり取りがタイムラインを埋め尽くす。
マスク氏は一時期、事実上トランプ政権の一員としてDOGE(政府効率化省)を率い、それまで政府が経済的にサポートしてきた人権擁護活動などを厳しい立場に追い込んだ。そんな人物が経営するXには、コンプライアンス上の問題はないのか。
恐ろしい場になり経営者にも問題が多いSNSだが、広告は今も活発だ。Xでは性的画像の投稿と同じ画面に、堂々と企業の広告が表示される。Facebookでも広告を見かけない日はない。企業は、こうした現状のSNSに広告を出稿し続けるのだろうか?