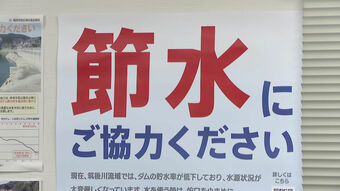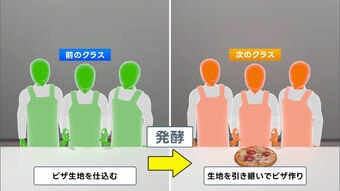全体の歴史像を正しくイメージさせる
全体像のイメージをきっちり残すのが、歴史学でも報道でも非常に重要なのです。ディテールは大事にするけど、細かいことを1つ挙げて全体を「こうだ!」と言い切っちゃうのは危険だし、捏造に近くなる。
南京虐殺がなかったと言っている人たちの主張は、ほとんどこれです。「虐殺がなかった」と言う人が周りにいらっしゃったら、「ああ……そんなことを思っちゃっているんだな、この人は」と呆れてかまわないです。
史料批判、引用の明記、先行研究の尊重、ミクロとマクロの峻別。どのお作法も、「自分に都合よく解釈しないための縛り」なのです。「私はこう思っている。その結論を見出すためにこのディテールを利用する」。そういう主張は、歴史学ではありません。全体像を描くために、ディテールを大事にしていくのが歴史学なのです。
だから、よくある「通説がこれでひっくり返った!」というのは、ほとんどがオーバーです。先行研究を全部ひっくり返すのは大変なことですよね。
ただ、全く知られていない史料が出てきて、通説の見方を考え直す必要が生まれることがあります。ある意味、歴史学の中の「特ダネ」と言っていいと思います。周りの歴史学者が「いやそんな大した話じゃないし、本当かどうかも分からない」と排除するものがほとんどですが、時にそういうことはあります。歴史はだんだんブラッシュアップされていくのです。
「歴史は現在と過去の間の対話」
最初に歴史学を学んだ時、「必ず読むべきだ」と言われた本があります。イギリスの歴史家、E・H・カーの『歴史とは何か』という岩波新書でした(清水幾太郎訳、1962年、税別860円)。2022年には新版が岩波書店から出ています(近藤和彦訳、税別2,400円)。この本に出ている言葉を、ぜひお伝えしたいです。
「歴史は現在と過去のあいだの対話である」
「過去は現在の光に照らされて初めて知覚できるようになり、現在は過去の光に照らされて初めて十分理解できるようになるのです」
【エドワード・ハレット・カー著『歴史とは何か』】
1961年にケンブリッジ大学でおこなった6回の講義がもとになっている。事実と解釈、歴史と科学、歴史における因果連関、歴史と客観性、進歩としての歴史など、歴史を考えるうえで最も重要なテーマが盛り込まれており、歴史学の最良の入門書。
歴史学とは、当時生きていなかった私たちがその当時を表現しようとするもの。現代の私たちの視点を通してしか描けない限界性もあります。だけど、それによって初めて過去は知覚できるようになる。そして現在も、過去の光に照らされて初めて理解できる。
「現在と過去の対話である」。歴史学を学ぶ上で、非常に重要な言葉です。そして私たちも将来、「あの時代に生きた人たちはこうだったんだね」と、歴史学の対象になっていくのです。
「歴史学」とは、こういったことを謙虚に、真面目に学ぶ学問です。「歴史」で遊んでいるうちはいいんですけど、それをもって先行研究を否定できるとは思わない方がいい。ですから、本田さんのポストは立派なものだと僕は思っています。
◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)
1967年生まれ。学生時代は日本史学を専攻(社会思想史、ファシズム史など)。毎日新聞入社直後に雲仙噴火災害に遭遇。東京社会部勤務を経てRKBに転職。やまゆり園事件やヘイトスピーチを題材にしたドキュメンタリー映画『リリアンの揺りかご』(2024年)は各種サブスクで視聴可能。5月末放送のラジオドキュメンタリー『家族になろう ~「子どもの村福岡」の暮らし~』は、ポッドキャストで公開中。