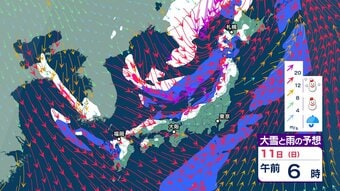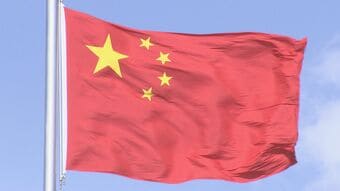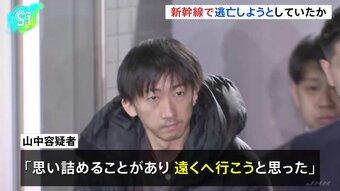事故から40年 原因の謎は解明されず
修理には、ほかに多くの作業員が関与している。男性には、修理で使用した「継ぎ板」が実際には切断されて出来たものという認識がなかった。誰が「継ぎ板」を2枚に切断したか、男性への取材では明らかに出来なかった。
一方、作業をした男性は123便の事故原因をめぐって過去の修理が日米で問題視されていた事実を全く知らなかったという。彼のもとに、そうした情報は届いていなかった。
もしひとりでも、修理ミスに気付いていれば、墜落事故を防ぐことが出来たかもしれない。男性は、123便の事故について「悲しいよ。多くの人が亡くなったんだから、それは悲しい。でも、事故は起きる。受け止めるしかない」と語った。
事故原因の“核心”は、40年経った今も解明されていない。
取材後記
航空担当の記者として、御巣鷹の尾根には何度も登った。山は秋から春先まで閉山されているが、取材のため閉山中の3月に許可をもらって登ったことが1度だけある。急斜面には雪が腰高まで残っていた。残雪を掻き分け、必死の思いで墜落地点にたどり着いた時、山肌に吹き付ける風の音しか聞こえなかった。8月の慰霊登山の人出とは違い「こんなに寂しい場所だったのか」そう感じたことを覚えている。
遺族とともに日米で事故を調査した関係者も高齢化が進んでいる。あの時何があったのか、関係者の証言や書類は貴重な歴史的資料となっている。航空機事故はいまも絶えない。今年6月にはボーイング787型機がインドで墜落、乗客乗員241人が死亡した。この事故でもアメリカの調査チームが現地に入っている。事故の教訓は生かされなければならない。そのために歴史は語り継いでいかなければならない。空の安全のために。それが事故を伝えるメディアの責務だと考えている。
※この記事は、TBSテレビとYahoo!ニュースによる共同連携企画です。