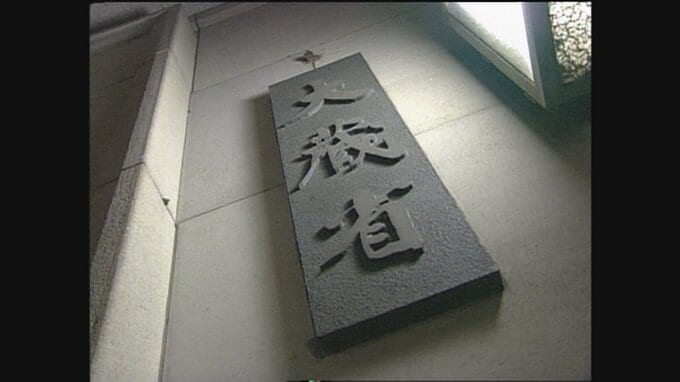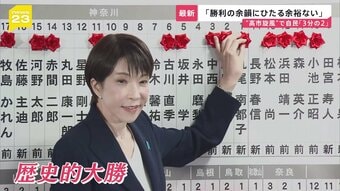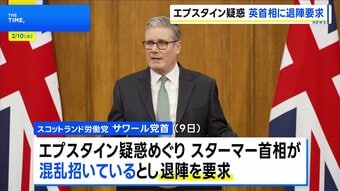「大蔵省キャリア」摘発へのネック
バブル期に膨張の一途をたどった銀行の不良債権。
その処理策を銀行に提供すべき立場にあった大蔵省の「金融検査官」が、あろうことか「接待漬け」によって不良債権を見逃し、金融処理の遅れをもたらしたことは明らかだった。
「ノンキャリアの金融検査官は“職務権限”が限定されていて、それに対するワイロの“対価性”すなわち“見返り”の構図が、比較的わかりやすかった。そのため、世間も“摘発価値があった”と受け止めてくれた」(元特捜幹部)
しかし、大蔵キャリアの立件となると、特捜部はさまざまな「雑音」に直面することになる。
一つは「職務権限」の問題だった。
キャリア官僚の業務は政策立案から政官界・財界との調整、さらに職務規定を超える広い意味での「ロビー活動」など多岐にわたっており、明確な「権限範囲」を定義することが難しい。キャリア官僚は、 ノンキャリアのように権限が限定されておらず、接待を受けることも“業務円滑化のための慣例”として黙認されてきた面がある。
こうした風土は、バブル期には、中央官庁のみならず、地方自治体まで広がっていた。
いざ大蔵キャリアを立件するとなれば、接待が「職務権限」と結びついているかどうか、つまり「接待の対価としての具体的にどんな見返りがあったのか」や、「社会通念上許される接待」と「過剰接待」の線引きなど、ノンキャリア以上に、詰めの捜査が求められた。
特捜現場は、摘発の基準をどう考えていたのか。
ある特捜検事はこう振り返る。
「接待を贈収賄事件として立件するしないの判断に重要だったのは、“つけ回し”があるかどうか、また特定の時期に接待が集中しているかどうかだったと思う」
「カネの動き、つまり過剰接待の事実が明確に出てくれば、職務権限につながる趣旨はあとからついてきた。裁判所も“接待は金品授受と同等”とみて、認定してくれると考えていた」
実際、「贈収賄事件」は東京地検特捜部にとって、いわば“十八番”とも言える得意分野であった。重要なのは、捜査段階でそうした贈賄側、ワイロを渡した側の明確な「自白」を引き出すことであった。
「贈賄側の正直な自白と、それを裏付ける証拠が揃っていれば、裁判所に有罪の心証を形成させることができると考えていた」(元特捜検事)
もう一つの「雑音」は、検察という組織特有の事情に関わるものだった。
大蔵省は「国家予算」を分配、管理する“官庁の中の官庁”であり、出身者の大半は東大法学部卒というエリート中のエリート。
その大蔵省の外局にあたる国税庁は、特捜部にとっては1993年の金丸脱税事件など多くの政治家の摘発でタッグを組み、二人三脚で歩んできた重要な「パートナー」でもあった。
国税庁や 各国税局(東京・大阪)の幹部ポストには大蔵省のキャリア官僚が就いていた。
脱税事案では、国税局が情報の端緒をつかみ、検察に告発し、東京地検特捜部が事件化するという「信頼関係」が敷かれていた。こうした経緯から両者には「持ちつ持たれつ」の関係が長年にわたって築かれていた。
また検察庁を退官した“ヤメ検”弁護士に対し、国税が顧問先の大企業を紹介するケースもあった。
さらには法務省が、予算配分を管轄する大蔵省主計局側を接待したり、逆に国税から法務・検察側を接待する例も一部で指摘されていた。
こうした背景から、法務省幹部や検察首脳の一部には大蔵省、とくに「キャリア官僚」への捜査に消極的な声が上がっていたのだ。