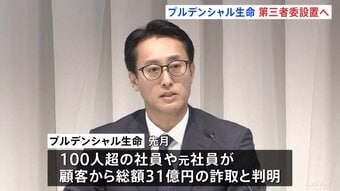「接待もワイロである」
大蔵省接待汚職捜査が佳境を迎えていたある日、東京地検特捜部副部長・山本修三は検察庁舎の地下食堂で、ある法務省幹部とばったり顔を合わせたときのことを記憶している。
「なんとかならないのかよ、と言われたので、どうにもなりませんよ、と受け流したと思う」(山本)
山本は「大蔵省から法務省にいろんなことを言ってきているんだろう」と受け止めた。
ある検察OBはこう語る。
「政治家を摘発できる最強の捜査機関・検察と、予算配分権を持つ最強の行政機関・大蔵省。護送船団行政の時代は、この二つがうまく噛みあうことで、日本の秩序は保たれていた」
「ロッキード事件やリクルート事件を指揮した吉永さん(土肥の前任の検事総長)も、大蔵省を国家システムの中核として守るという大前提は持っていたと思う。とは言え、吉永さんが検事総長の時代に大蔵省汚職が発覚していたとしても、贈収賄という実質犯の証拠が出ている以上、“大蔵キャリアを接待で立件するのは辞めろ”とは言わなかっただろう」
実際、東京地検検事正の石川達紘(17期)や特捜部長の熊﨑勝彦(24期)には「接待」を「ワイロ」とみなして、贈収賄事件を立件した捜査経験もあった。
石川は1986年、通産省のキャリア官僚が業者から340万円の接待を受けて便宜をはかっていた「撚糸工連事件」で、悪質な「つけ回し」の実態を摘発している。同事件ではロッキード事件以来10年ぶりに国会議員が摘発されている。
また熊﨑は、1988年の「総理府汚職事件」で、元広報担当参事官を100万円余りの接待で立件。さらに1989年の「リクルート事件」では、「飲食接待」や「ゴルフ旅行」など130万円余りの接待を受けた労働省(現、厚生労働省)の官僚を収賄罪で摘発している。
今回の大蔵省接待汚職では、それら過去の事件をはるかに上回る規模の接待が行われていた。
こうした前例を踏まえ、「接待もワイロである」という認識は、捜査実務において、すでに検察内では常識となって根付いていた。「刑法197条」に規定されている収賄罪は、「ワイロを現金だけでなく、人の需要・欲望を満たす、あらゆる利益」と定義しているからだ。
「現金さえもらわなければ、刑事責任を問われることはない」というのは、公務員側の勝手な解釈に過ぎなかった。
熊﨑は筆者にもこう語っていた。
「接待に関しては、検察よりも裁判所の方がよほど厳しく捉えている。キャッシュが出てきてなくても、裁判所は“接待イコール金品授受”とみなしている。だけど、特捜部は“単なる接待”だけでは立件しない。きりがないやろ」
「“つけ回し”があることと、その公務員しか持ちえない秘密情報の漏洩といった行為が伴っている“接待プラスアルファ”がなければ、やらないよ」