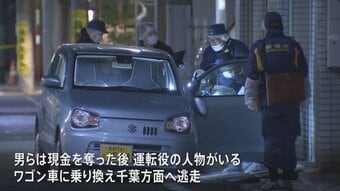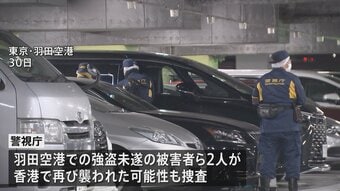一昔前は窮地に立たされていたラジオだが、15年前に誕生したラジコ(radiko)によって存在感を取り戻しつつある。radiko経営陣が6月に新体制になったのを機に、設立当初に電通から出向して来て以来今日までラジコを育て上げてきた青木貴博会長にメディアコンサルタントの境治氏が話を聞いた。
ラジオが今熱い!マスメディアの中でも最も元気がなかったはずのラジオが、今は最もホットなメディアになりつつある。その牽引役は、スマホやPCで気軽にラジオが聴けるラジコだ。どこでも聴ける上にタイムフリー機能でいつでも聴ける。有料だがエリアフリー機能で放送エリア外の番組も聴ける。ラジオ受信機を見たことがない若者たちが、ラジコを使って深夜番組を翌日に熱中して聴いている。
そのラジコが2010年にサービスを開始してから、今年で15年。日本のラジオ業界に革命をもたらしたこのサービスは、どのように生まれ、成長し、そして未来に向かうのか。6月に株式会社radikoの社長を退任して会長に就いた青木貴博氏にインタビューした。ラジコを立ち上げから15年間支えてきた青木氏の話は、他のメディアにとっても学びの多い、中身の濃いものだった。
ラジコはなぜ2010年にスタートできたのか
境 ラジコの立ち上げは放送コンテンツの配信事業として、世界的にも早かったですね。どのような経緯でスタートしたのでしょうか?
青木 ラジコを考案したのは元朝日放送技師長であり、現当社最高技術顧問の香取啓志(かんどり・けいし)さんと、元電通で現在関西大学教授の三浦文夫さんです。お二人はラジオ放送のIPサイマル配信の始動とラジコサービスの実用化に貢献したことが評価され、第68回前島密賞を受賞されました。
ラジコを立ち上げる前に、香取さんと三浦さんは、いくつかのラジオ局さんとインターネットでの配信を試みていました。ただ、個別の局でやっても広がりません。業界全体で配信する仕組みについての話し合いが始まりました。
境 2008年に大阪のラジオ局によりRADIKOの名称で試験配信が始まっています。なぜ大阪から始まったのですか?
青木 香取さんは大阪の朝日放送、三浦さんも電通関西にいらしたということもありますが、それとは別に、いきなり東京のラジオ局さんが放送コンテンツを通信に載せる準備をするのは難しい部分もあり、じゃあ大阪からやってみようということになりました。
境 2010年に東京のラジオ局も加わり、株式会社radikoとして正式にスタートしました。なぜラジオがテレビより先にこうしたサービスを実現できたのでしょうか?
青木 危機感だと思っています。ラジオ広告費の過去最高値は1991年の2406億円でした。それがラジコを始めた2010年には半分近い1299億円になっています。これほど危機感を感じる数字もないでしょう。局の数はほぼ変わっておりませんので、1局あたりの収入は半分になりますからね。
境 権利許諾はスムーズに進んだのですか?
青木 大阪で立ち上がった時は、データをやり取りする際のルールを定めた「プロトコル」に、多数の受信者に向けて効率的なデータ配信を可能にする「IPv6マルチキャスト方式」を採用しました。この方式ですと、「放送」の概念と同じになります。そのため、法的に権利許諾の必要がありません。もちろんマナーとして各音楽業界団体や個別権利者などに報告はしました。
一方、東京も含めて正式スタートする時には、より汎用性が高く、1対1の通信が可能になる「IPv4ユニキャスト」を採用しました。インターネット上で聞けるようにしないと意味がないためですが、こちらの方式にすると権利の考え方が変わります。「放送」ではなく「通信」の扱いになり、権利許諾が必要になります。この許諾をいただく作業は、本当に大変でした。
境 その権利処理には何年くらいかかったのでしょうか?
青木 大阪でマルチキャストで始まり、ユニキャストに移行するため皆さまにご理解いただくまでに1年以上はかかったと思います。
境 音楽関係の権利者の方々も危機感を共有してくれたのでしょうか?
青木 それはあると思います。実感として、音楽関連で言えばJASRAC、Nextone、音事協(日本音楽事業者協会)、音制連(音楽制作者連盟)、日本レコード協会やCPAR(実演家著作隣接権センター)。各団体がラジオをすごく応援してくださっている実感があります。
それぞれの団体の上層部の方々がラジオ世代だったのも大きいでしょう。当時の50代から60代前半ぐらいの世代の皆さんが10代の頃は、ラジオが自分だけのメディアだったと思います。ラジオで育っていらっしゃるので特別な感情がある。こんなところで終わってる場合じゃない、みんなで応援してやろうとの空気はありました。それは大変ありがたかったですね。

境 NHKは独自にラジオの配信サービス「らじる★らじる」を持っていますが、2019年からラジコでも聴けるようになりました。NHKが参加した経緯は?
青木 ラジコは民放局で始まったサービスですが、NHKさんにも定期報告に行ってました。同じラジオ業界として、いろんな会話をしてきましたよ。ユーザーの立場で考えれば民放とNHKが入れば、これまでのラジオ受信機と一緒です。その姿を理想に議論をしながら、NHKさんにお入りいただく日が来ました。
境 NHKはCMが入らないことが問題にならなかったのですか?
青木 ならないですね。もちろん、ラジコでNHKを聴けばCMは入りません。ただ少し気になるのは、アプリ全体の冒頭の広告はどうなのか。そういったことについて議論はします。我々としてはそれがセールスできないと困ってしまいますからね。